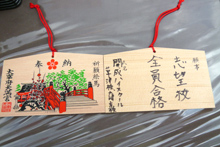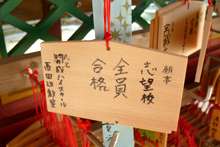成功は成功のもと
2011 年 10 月 24 日 月曜日 こんにちは。
「失敗は成功のもと」この格言が真理であることは、疑う余地もありません。「失敗を反省し、それを反転させ、次なる行動に反映させることによって、自らに成功をもたらす。そうすることで、失敗はむしろ「よい経験」として活かされる。」かの発明王エジソンが電球のフィラメントに用いる素材を模索した過程は、まさにその好例としてあまりにも有名ですね。
ところで、先の格言に加え、「成功は成功のもと」これもまた真なりや、と私は思うのです。自らの成功体験を改めて客観的に吟味し、その原理なり法則なりを抽出し、それを意識的に実践することで、自分なりの「成功パターン」を確立していく。こうした視点も、一つことに取り組み、成就する過程において、欠くことのできないものでしょう。
私は、テスト結果を受けての生徒面談の際に、ある科目で大きく点数を伸ばした生徒に対し、この「成功のもと」を必ず聞くようにしています。「何を、どのように勉強したの?」「どれくらい取り組んだの?」このように尋ねられ、生徒はその勉強の仕方を客観的に認識し、「成功パターン」として次なる取り組みの指針としていきます。その生徒にとって、これほど適した勉強法はないでしょう。すでに自ら実証済みなのですから。
同じ過ちは繰り返すべきではありませんが、同じ成功は繰り返すべきでしょう。特に勉強に関しては、反省のみならず、成功事例の中にも、宝物が豊富に埋まっているのです。
具体的事例から法則性を見出し、それを新たな局面に対処する術とする―これはまさに「科学」の根本ですね。