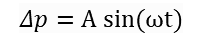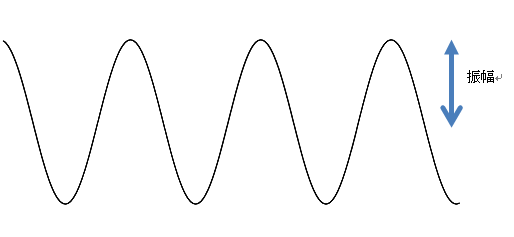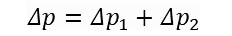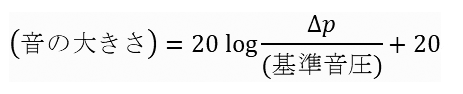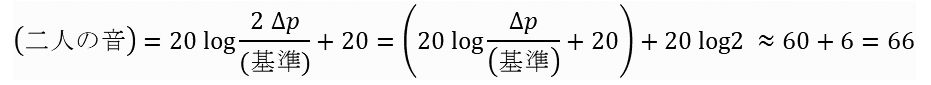受験シーズン真っ盛り
2018 年 1 月 29 日 月曜日センター試験も終わり、国公立の出願も終え、息つく暇もなく関関同立の一般入試が目前となってきました。毎日がめまぐるしく、やるべきことは山積みですが、一つ一つを丁寧にこなしていかねばなりません。さらにインフルエンザも全国規模で流行の兆しを見せ、受験生にとってみれば、健康面での注意点もいっぱいです。
さて、開成ハイスクールでは高3生の国公立2次対策授業が始まり、教室や自習室では受験生が毎日熱心に勉強に取り組んでいます。中にはかなりハードルの高い生徒もいますが、一人でも多くの生徒が第一志望の大学に合格できることを祈っています。
また高1・2生も、1月14日に行われたセンター試験の問題にチャレンジするイベント「センターチャレンジ」で頑張りをみせてくれて、中には英語で8割を取った高2生もいました。その日のうちにしっかりと自己採点をし、受験生としての心構えを学んでいました。今から来年が楽しみです。
今この文章を作成している間にも、高3生が国公立出願に関する相談に来てくれています。関西圏の大学入試は、私立大学も含めて全国的にみても激戦区になります。センター試験で上手くいった人、本来の力が発揮できなかった人、結果はさまざまではありますが、これからの目標達成に向け全力でがんばりましょう。
受験生のみなさん、あとひと踏ん張りです。