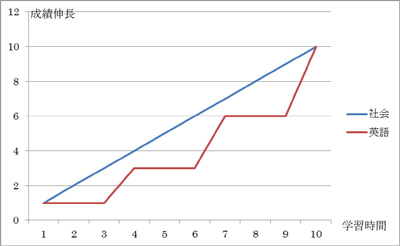もうすぐ夏休み!!
2013 年 7 月 16 日 火曜日みなさん、暑い中いかがお過ごしでしょうか。今年もすでに35度を超える猛暑が各地で記録されています。熱中症にならないようにこまめな水分補給をしましょう。暑いところを避けたいなら、開成ハイスクールの自習室がお勧めです!快適な中で勉強もはかどることでしょう。学校から夏休みの宿題が大量に出されることでしょうから、宿題も終わって一石二鳥です。ぜひ、活用してください!!
さて、夏休みが始まります。この夏休みをうまく使うことで、成績を飛躍的に伸ばすことができます。家の中でのんびりしている時間があったら、少しでも机に向かって勉強しましょう。では、学年別に見ていきましょう。
一年生は、高校に入って初めての夏休みです。一学期で習った箇所をきちんと復習しましょう。特にテストで間違えたところは要チェックです!さらに、二学期に進む単元を予習できればなおよいです。開成ハイスクールの授業と並行しながら進めていくとよいでしょう!
二年生は、ちょうど高校生活の折り返しとなります。まずは、一年生の復習をやりましょう。入試で出題される問題は意外と一年生の時の内容がたくさん出てきます。その上で、一通り済んでしまったら、入試問題を解いてみるのもいいかもしれません。もちろん、今の時点では、あまり解くことができないと思いますが、自分の弱点や入試の傾向を知るにはいいと思います。
三年生は、受験まで残り半年と迫っております。入試問題を解くための必要な知識(公式や解法など)をたくさん蓄えて夏休み以後の入試演習に備えておく必要があります。ここを中途半端にしてしまうと、過去問が解けない上に、「焦り」の原因にもなってしまいます。
夏休みはおよそ一か月あります。この間に力をつけたい人、もう一度やり直したい人などいろいろな人がいると思いますが、とりあえず机に向かって、ペンを持たないと何も始まりません。勉強する際はぜひ、開成ハイスクールの授業や自習室をご利用ください!
開成ハイスクール数学科 鈴木 悠太