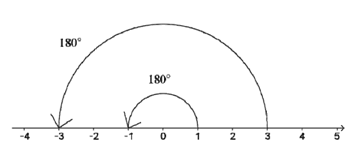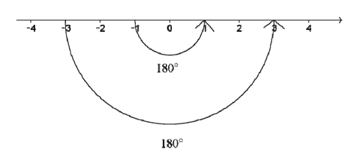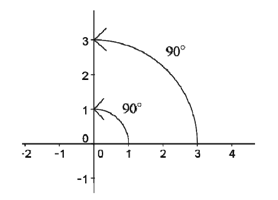暗記方法をもう一度振り返ってみること
2013 年 6 月 10 日 月曜日とうとう梅雨に入ってしまいました。
この時期が嫌いで、どう快適に過ごそうか、毎年悩みます。
高3生と面談していて毎年痛感するのは、暗記の作業が中々進まないことです。
「覚えてもすぐ忘れる」これは多くの生徒が言う悩みの一つです。
ある生徒は、「忘れてしまうこと」を極度に恐れていました。
忘れるのは当然です。人間ですから。
忘れるのを想定して、暗記のルーティーンを組みましょう。
とにかく毎日実行することが肝心です。
特別な意識を捨て、1つの「習慣」にしてしまうのです。
ある生徒は、「いつ暗記するのが効果的か?」と悩んでいました。
「寝る前に暗記→起きてから復習」を繰り返すと、早期に長期記憶になるようです。
短い時間(5分程度)から始めましょう。
これは、多くの生徒が試して実感しています。
またある生徒は、「どうしても覚えられない単語」はどうしたらいいか?と聞いてきました。
どうしても覚えられない単語・フレーズは放置しないで下さい。
ノートにまとめて書いておき、最低でも2日に1回はそれを見て唱えます。
必ず声に出して確認しましょう。
特に英単語は、発音して覚えることが不可欠です。
読めない・発音できない単語は確実に忘れてしまいます。
古典の単語は、成り立ち・漢字などを暗記のヒントにして覚えましょう。
事前に約束した課題の単語テストをしてみたら、全然書けなかった生徒がいました(汗)。
自分がしっかり「暗記できているか」をチェックすることは大切なことです。
週に2回はランダムチェックして自分の暗記ができているか確かめましょう。
私たちの各教室には、単語テストを自由に範囲指定して作ることができるツールがあります。
詳しくはスタッフに声をかけてみて下さい。
開成ハイスクール英語科 大道英毅