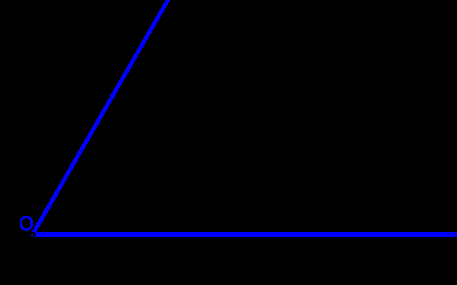出会いと別れ
2013 年 4 月 1 日 月曜日 大学入試を終えられた皆さん、お疲れ様でした。高校入試を終えられた皆さん、お疲れ様でした。同じ挨拶に聞こえるかもしれませんが、実は全然意味が違うのです。大学入試を終えられた皆さんの大半は大学生になり、自分のやりたいことを大学生活で始められることでしょう。高校入試を終えられた皆さんは高校生になり、自分のやりたいことを見つけるために、高校生活を始められることでしょう。
私たちは、開成ハイスクールという高校生を対象とした部門に関わっているので、大学生になられた皆さんとは、本当にお別れになります。しんどくて辛い大学入試に挑むために共に過ごしてきた時間は、私にとっても貴重な財産です。志望校合格が決まって、笑顔で報告に来てもらえる瞬間ほど気持ちの良い事はありません。今年も数多くの報告を頂き、本当に感謝しています。これからは、本当に自分のやりたいことに打ち込み、社会人として世の中に羽ばたいていって下さい。そして何かにぶち当たった時に、また相談に来てもらえたら嬉しいです。
それから、高校入試を終えられた皆さん、これからは高校生としての生活が始まります。高1準備授業に参加して頂いた生徒さんは、既に高校の授業というものがどういうものなのかを体験して頂いておりますので、その大変さはご理解されていることと思います。まだ高校に受かってから次のステップに向けて、何も動きだせていない生徒さんは、そろそろ重い腰を上げて動きださないと、それに慣れてしまって本当に動けなくなってしましますので、注意をして下さい。既に動き始めている生徒さんとの差がどんどん広がって取り返しがつかないことになってしまいます。私はそのような、まだ冬眠から覚めていない生徒さんとの出会いを心待ちにしております。どうせやるべきことなのです。後々楽をするためにも、やるのは今です。新学期1回目の授業から、皆さんとお会いできることを楽しみに待っています。
開成ハイスクール英語科 濱田健太郎