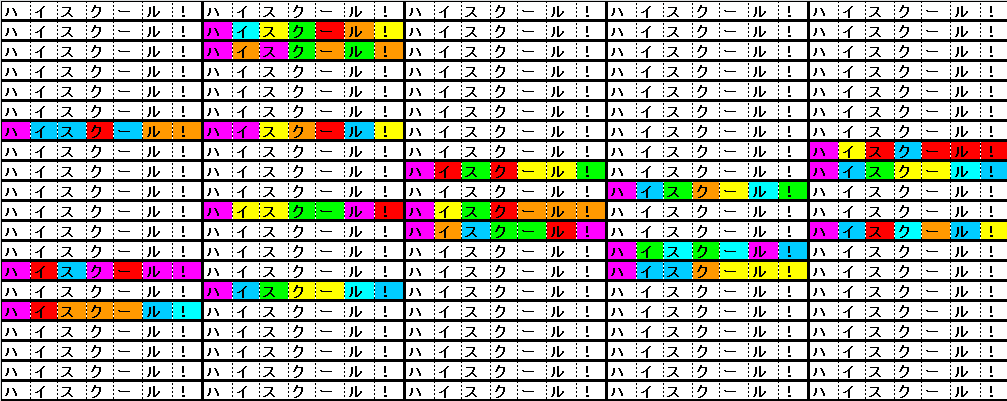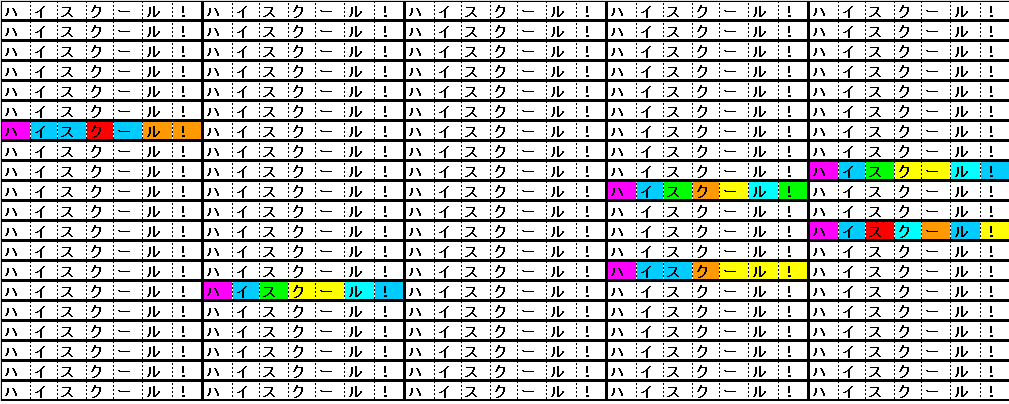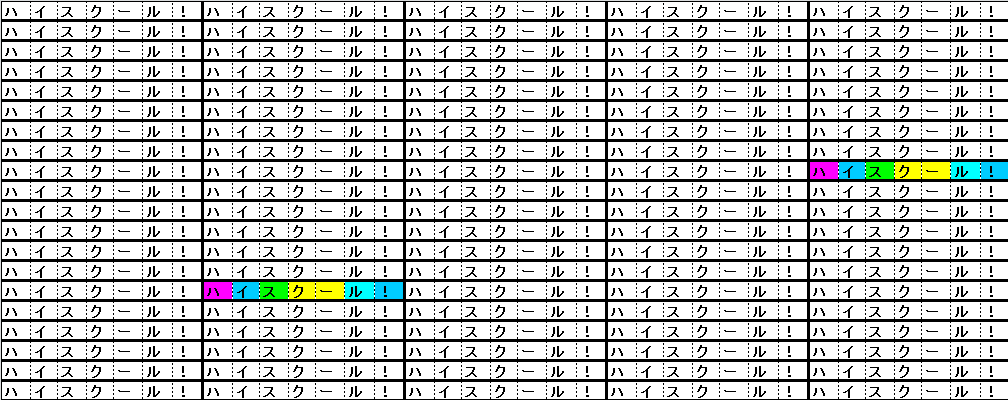睡眠のメカニズム
2016 年 10 月 17 日 月曜日みなさんは普段、どのくらい睡眠時間をとっているでしょうか。
最近では、子供も大人も就寝時間が遅くなったり、不規則になったりする傾向がありますが、心身を健康に保つためには、十分な睡眠をとるべきです。
睡眠は、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」の異なった2つの睡眠状態で成り立っています。
ノンレム睡眠は、「脳の休息と体のメンテナスのための睡眠」です。ノンレム睡眠中の脳は完全に休んだ状態になり、起きている間に得た情報の中から不要な情報(怖かったことや不愉快なことなど)を眠りながら緩和・消去しています。また、起きている間に傷ついた体のメンテナンスも行われています。傷ついた細胞の修復や疲労の回復、体の成長などを担う「成長ホルモン」は睡眠中にしか分泌されませんが、その分泌量は眠り始めて最初のノンレム睡眠に最も多く分泌されます。
それに対して、レム睡眠の最大の特徴は、眠りながら非常に速い速度で眼球が動く急速眼球運動(Rapid Eye Movement)が見られる点で、この頭文字から「REM Sleep(レム・スリープ)」と呼ばれています。
レム睡眠中の脳は、起きている時以上に活発に活動しています。起きている間に得た大量の情報から必要なものと不要なものを眠りながら整理し、必要な記憶の定着や記憶を引き出すための索引作りを行っていることが、近年の研究で明らかになっています。つまり、昼間に体験した出来事や、学習によって得た知識などの大切な情報を、レム睡眠中に整理しながら記憶として脳に焼き付けているのです。脳が活発に動いているので、この時に目覚めると気分がすっきりします。
私たちの睡眠は、これら性質の異なる2種類の睡眠で成り立っており、約90分周期で一晩に4~5回、一定のリズムで繰り返されています。
睡眠直後の3時間はノンレム睡眠の割合が多いため、ホルモンの分泌や疲労をとるためには、最低でも3時間の睡眠は必要です。しかし、13~18歳の心身ともに成長する時期は、睡眠も多く取る必要があります。
それらを含め、学生にとって理想の睡眠時間は6時間か、7時間半といったところでしょうか。起床したい時間から逆算して何時に寝れば睡眠時間を快適に保てるか考えることも必要ですね。
人間の頭が働くのは起きて約3時間後だと言われています。特にテスト当日は、1時間目が始まる前に脳を最高の状態にしておくべきだと思います。1時間目が8時半に開始するとして、起きるのは5時半、6時間睡眠をとるのであれば23時半、7時間半睡眠をとるのであれば22時に寝れば、翌日のテストはいい状態で臨むことができるでしょう。
不規則な生活をおくっているのであれば、まずは生活習慣を見直してみることから始めるべきです。
テスト前日に徹夜するのは、無意味だといってもいいでしょう。テスト直前期は体調管理も必須です。慌てることがないよう、常に日頃の学習を大切にしたいですね。
開成ハイスクール数学科