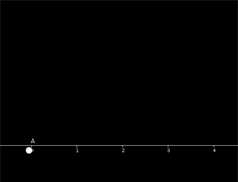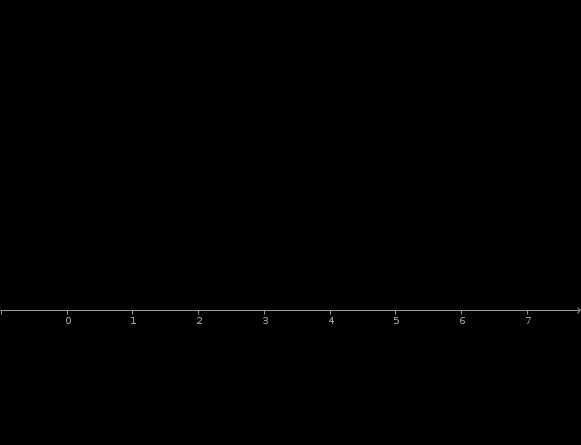来年度は数学で新課程の入試が始まる.数学Iには「データの分析」が入り,数学Cが廃止され「行列」や「1次変換」はなくなる.そのかわり,数学Ⅲには「複素数平面」がまたもや復活する.「複素数平面」は一度消え,復活し,また消え,また復活した.それに対して,「1次変換」は登場し,消え,復活し,また消えた.前回は「行列」は残ったが,今回は「行列」まで消えてしまった.しかし,こんなにコロコロ変えるのは,いったい何のためなのか?参考書の売上を確保するためか?文部科学省のお役人が「複素数平面」マニアなのか?それにしても「行列」や「1次変換」を高校数学から全面的に消滅させると,今年度の受験生は大学入学後に「線形代数学」でこれまでの受験生よりもはるかに苦労するのだろうな,と先のことまで考えてしまうが,まずは大学に入学しないと話にならない.
こういう年度の前後の受験生は気の毒である.旧課程最後の受験生は浪人をできるだけ避ける選択をしようとし,新課程最初の受験生は,過去問がなくて困る.なお,私も旧課程最後の受験生だったし,浪人したから,新課程最初の受験生でもあった.だから,不安な気持ちは分からないこともない,と言いたいところだが,私のときは,一浪は別に珍しくなく (私の高校のクラスは半数が浪人している),ゆとり教育への進行中だったので,「新課程の受験生は,君たちよりもはるかにできないから,変に妥協して大学に入学するより,思い切って (?) 浪人して,それで本当に行きたいところに行きなさい」などと変な煽られ方をしたぐらいなので,今とは深刻さが違うだろう.
さて, 2015年度の入試がどうなるかを考えてみる.今回とよく似た事例は,1997年度入試であろう.この年から「1次変換」が「複素数平面」に切り替わった.この前後におけるいくつかの大学の対応を列挙してみる.なお,当時は旧課程の「1次変換」も新課程の「複素数平面」も文理共通の範囲であったことには注意されたい.当時の入試は「1次変換」の百花繚乱時代でもあった.私が受験したときも4問中2問が「行列」「1次変換」といった具合であった (なお,残りの2問はいずれも「解の配置問題」である.ひどい偏りである).あと,「1次変換」と「複素数平面」とで共通している内容は,平面上での点の回転+拡大移動を扱えるという点である.つまり,回転+拡大の問題は,どちらの知識でも扱えるということである.
1. 東京大学: 1997年度はさりげなく出題していない.1998年度に回転+拡大の問題が出題され (ただし,「1次変換」のアプローチの方がやや有利か),本格的な「複素数平面」を知らない限り解けない問題は1999年度に初登場する.
2. 京都大学: やはり複素数平面の知識がないと解けない問題は1999年度にやっと初登場する.1998年度にも複素数に関する問題が出題されているが,これは複素数平面の知識は必要ない.なお,1996年度入試を総括する当時の「大学入試懇親会」において,京都大学の先生が,旧課程と新課程の共通部分,すなわち,回転+拡大でアプローチできる問題を出題すると言われていたらしいが,直後には出題されてはいない.あと,参考までに旧課程最後の1996年度入試に,まさにその回転+拡大でどちらでもアプローチできる問題が出題されていた (これは必ず解いておくべし.京都大学は過去問をよく研究している受験生にはご褒美が出る — すなわち類似の問題が出題されることがよくある).一応,それがその後の京都大学の傾向を示唆したものと見られていたのだが……
3. 大阪大学: 1997年度,1998年にすぐさま回転の問題が出題されている.これらはどちらの課程の受験生でも対応可能ではあったが,97年度は旧課程やや有利,98年度は新課程が完全に有利な設定に思える.複素数平面の知識がない限り解けない問題は2001年度に初めて登場する.そもそも大阪大学は,回転+拡大が大大大好きな大学なので,別に新課程でなくても出題される可能性は高いといってよい.
4. 神戸大学: 1997年度に,複素数平面を知らずには解けない問題がいきなり出題されている (逆にレベルは標準的だが).選択問題にもなっていない.その後もほぼ毎年出題されている.ということで,かつての神戸大学は,複素数平面が大好きな大学であったのだが…
5. その他: 北海道大学は1997年,98年度には選択問題として出題した.東北大学は2000年度になって初めて出題された.一橋大学はいきなり1997年度に必須問題として複素数平面の問題を出題.東京工業大学は 1999年度に初めて出題された.名古屋大学は1998年度に初めて出題,しかしその後はほぼ毎年出題.九州大学は1997年度から選択問題の一つとして出題された.それ以外には,1997年度入試に限ると,横浜国立大,岡山大,高知大などで比較的難し目の問題が出題されていた.
正直言って,もっと回転+拡大の問題が多いかと思っていたのだが,意外に少なかった.回転+拡大以外に目立った問題は,複素数平面上の三角形に関する問題であった.ということで,新課程入試では複素数平面上の回転+拡大に加えて,三角形の形状問題についてもとくに注意が必要である.でも,やはり最初の2年間は,一部の大学を除いて,比較的穏健な出題をしようとしているということもわかる.
しかし,センター試験は,概ね新しいことをやるときには何かが起こることが多いので (私のときには数学で事件が起きた.これによって人生を変えられた人も周りには多かった),少々のことで動じない図太さが今年の受験生にはとくに必要です.夏に勉強して,図太くなってください.
開成ハイスクール 片岡尚樹