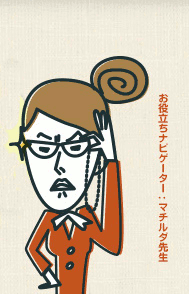こんにちは。
高校1年生・高校2年生のみなさんに見てもらいたいものがあります。
以下のリストは私が担当している、ある高3生の2014年5/31~6/6の1週間の学習記録です。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
5/31(土)
13:30-15:00 京阪数学テキスト3問
15:00-16:30 倫政黄色本20ページ
16:30-17:30 倫政問題集4ページ
17:30-18:45 倫政黄色本20ページ
18:50-22:00 数学の授業
6/1(日)
9:00-9:30 古典単語315 1~72
9:30-11:30 数学4問
11:30-11:50 微分積分の公式の確認
13:30-15:30 倫政の黄色本 20ページ
15:30-16:20 センター論説文1問
17:10-18:10 センター漢文4問
18:20-18:50 シス単 600~725
18:50-20:30 漢文の授業
23:00-24:30 センサー地学10ページ
6/2(月)
7:05-7:35 シス単600-850
16:30-18:50 地学センサー10ページ
18:50-20:30 倫政黄色本40ページ
20:30-21:10 数学3問
21:20-21:40 センター小説文1問
21:40-22:10 現代文記述プリント
23:45-24:30 倫理問題集4ページ
24:30-24:45 古文単語
24:45-25:00 ヴィンテージ
6/3(火)
7:00-7:15 古文単語
7:15-7:30 シス単
16:30-17:00 英語の要点
17:00-18:00 倫政黄色本10ページ
18:00-18:35 地学センサー8ページ
18:50-22:00 英語の授業
22:10-22:30 センター論説文1問
25:30-26:00 英語和訳問題
6/5(木)
7:00-7:30 シス単
(空き時間活用)センサー地学3ページ
16:10-17:10 センサー地学7ページ
17:10-18:05 塾の国語の宿題
18:05-18:35 センター論説文1問
18:50-22:00 国語の授業
23:30-25:00 古典講読の予習
25:00-25:30 倫政黄色本10ページ
6/5(木)
7:00-7:30 シス単
(空き時間活用)センサー地学3ページ
16:10-17:10 センサー地学7ページ
17:10-18:05 塾の国語の宿題
18:05-18:35 センター論説文1問
18:50-22:00 国語の授業
23:30-25:00 古典講読の予習
25:00-25:30 倫政黄色本10ページ
6/6(金)
7:00-7:30 ヴィンテージ
(空き時間活用)倫政黄色本10ページ
地学センサー3ページ
16:25-16:30 地学センサー1ページ
16:30-18:10 センター数学6問
18:10-18:40 センター小説文1問
18:40-19:30 古典文法の確認、漢文句形の確認
19:30-19:40 フォーカス和訳
19:40-20:45 塾の英語の授業の復習
20:45-21:20 現代文2次対策プリント
21:20-21:50 日本史復習
11:45-12:20 シス単3章
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
さあ、みなさんはどういった印象を持ちましたか?
まだ受験勉強を始めたばかり…の高3生としては、かなりやり込んでいると言えます。
この生徒は高校2年生のときから担当していますが、勉強に対して非常にストイックに取り組んでくれています。
そんな彼女はいま、模試で大阪大学の合格圏内。
受験生に対して唯一平等に与えられているもの、それこそが「時間」です。
全国の中高一貫校生・浪人生・公立高校生と戦わなくてはならない大学入試では、スタートの早さが何より重要です。
上記の生徒は本格的な受験対策を高2の夏の終わりから始め、私との面談で決めた課題を必ずこなしていました。
…とは言え、何事もやり始めの頃は不安定なものです。自転車に乗れるようになったときのことを思い出して下さい。漕ぎ出しではフラフラして転ぶこともありますが、スピードが出てくると走行状態を維持できますよね?
勉強もそれと同じです。「勉強するのが普通」という感覚をいかに早く身につけるかが勝負の分かれ目です。
この生徒に「どうしてそんなに頑張れるの?」と聞いたことがありますが、「するのが普通になっているから、しないと何か不安になる」という答えが返ってきました。確かに、習慣になっていること、例えば入浴や歯磨きを怠ると、嫌な気分になりますね。
各教室では、受験について担当の先生が親身になって相談を受け付けます。
早期に対策を始めて、ライバルに一歩差をつけましょう!





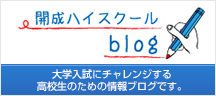
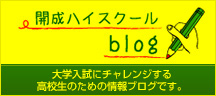
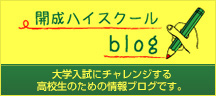 「青色30%」
「青色30%」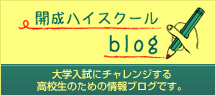 「青色50%」
「青色50%」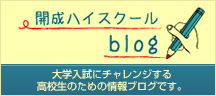 「青色70%」
「青色70%」