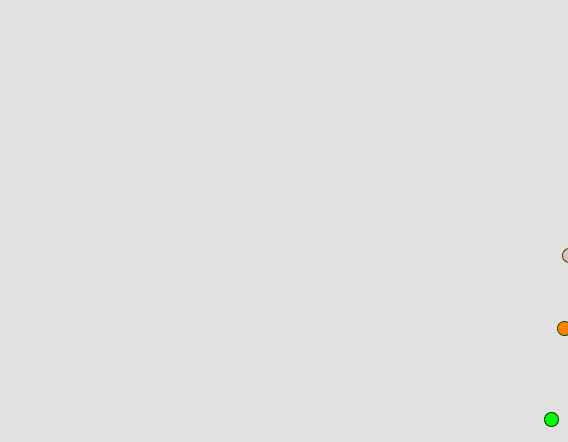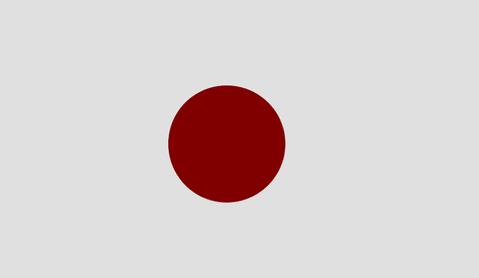数学と科学・技術 その5
2015 年 6 月 8 日 月曜日みなさん、こんにちは。
今回は、複素数から話を始めたいと思います。少し準備が長いので、結論を知りたい人は、最後の方を先に読んでください。さて、複素数とは、高校で初めて習う数で、二乗すれば、なんと-1になる数 i (虚数単位といいます)を使って書ける数のことです。不思議に思う人もいるでしょうが、まずはこの数を使ってお絵かきをしてみましょう。お絵かきといっても、数学を使ったお絵かきなので、ある程度のルールをもった書き方をします。
まず複素数として、z=-3+2i を考えてみましょう。この複素数に対して、座標 (-3,2) に点を書きます。次に z=-2+2i を考えましょう。同様にして、座標 (-2,2) に点を書きます。さらに z=-1+2i を考えましょう。そして座標(-1,2)に点を書きます。こうすることで、平面上に横一直線に並んだ点が書けます。
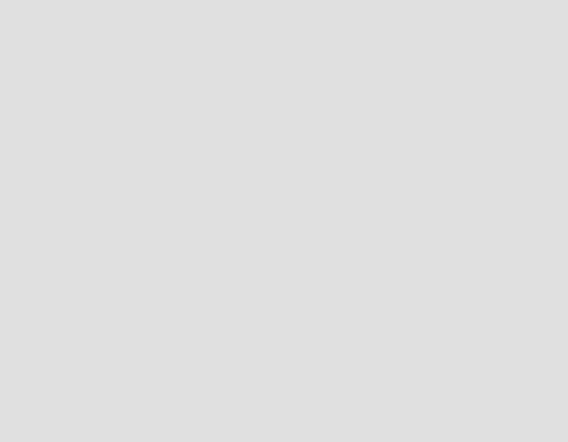
「だから、どうした。当たり前ではないか」と思う人もいるかと思いますが、では次のようにしたらどうなるでしょう。今は、複素数 z を考えましたが、zの2乗 を考えたらどうなるでしょう。
![]()
と計算できるので、(5,-6),(0,-8),(-3,-4),⋯ と点を書いていきますが、ではどんな絵が現れるでしょう。実は次のようになります。
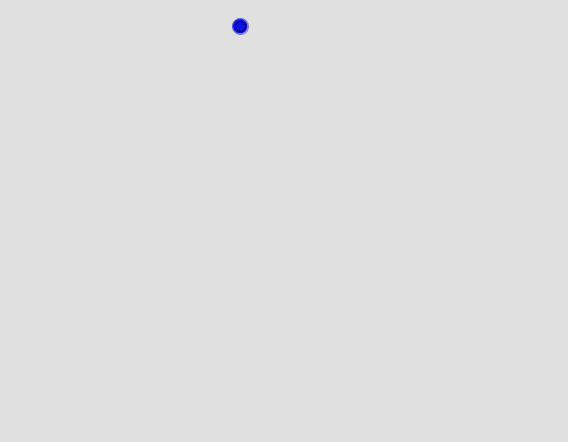
なにか、くねっと曲がった曲線が出てきましたが、これは放物線になることが分かっています(高校数学でよく見かける放物線が横倒しになっています)。では次に、上のアニメーションでは、虚数単位 i の前の係数を 2 にしていましたが、1にしたり、0.5にしたり、0.1にして、同じことをしてみるとどうなるでしょう。次のように多数の放物線が一度にかけてしまいます。
それぞれの点がギュッと集まってきて、そのあと散っていく様をみると、何か可笑しいですね。いや、可笑しいどころか、何がしたいのかわからないし、そもそも「数学と科学・技術」という題名はどこにいったの?と思っている人もいるでしょうか?では、最後に二次方程式の解の公式みたいなものを使ってみましょう。
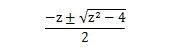
となる点を書いていきます。複素数のルートって何、という疑問はここでは深入りできないので、省略します。この形だと次のようなアニメーションができます。
真ん中にある茶色い丸はわかりやすくするために書いているので無視してください。動いている点が今考えている物です。10種類の動く点があるのがわかると思いますが、どのように見えるでしょうか?実は、この点の動きは、左から右に水が流れているときに、真ん中に丸い丸太を置いた時の水の動き(流れ)になる、ということが分かっています。その昔、鴨長明は「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と詠みましたが、そんな水の流れが、想像上の数と思われていた複素数と結びつくなど誰も想像しなかったでしょう。そう、勉強することは、人間の苦心に満ちた文化を学ぶことでもあるのです。
開成ハイスクール数学科 村上豊