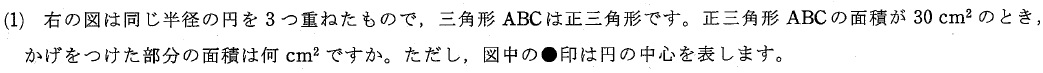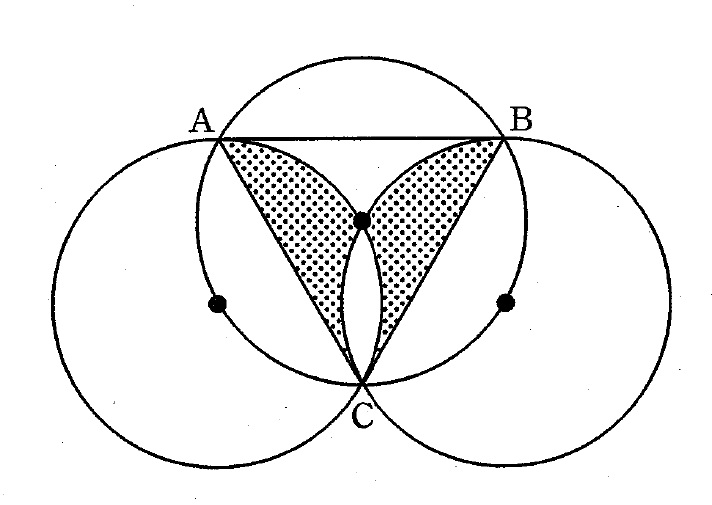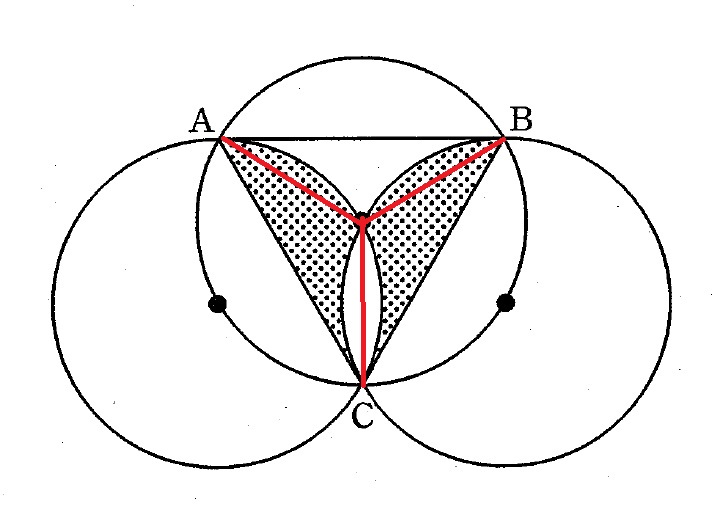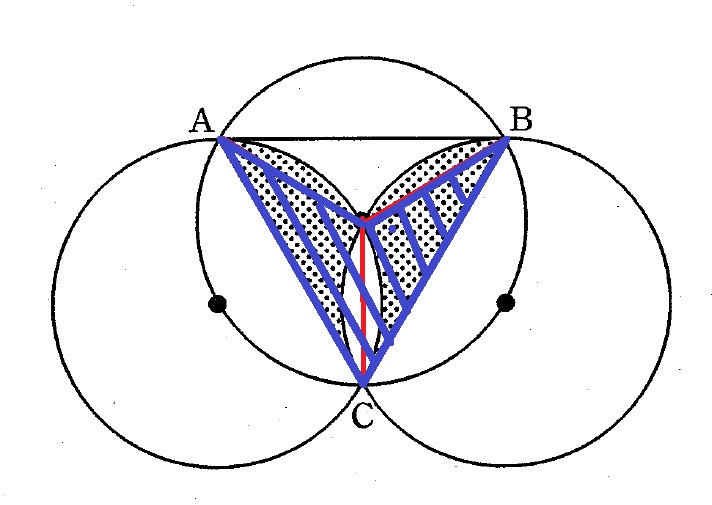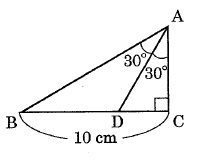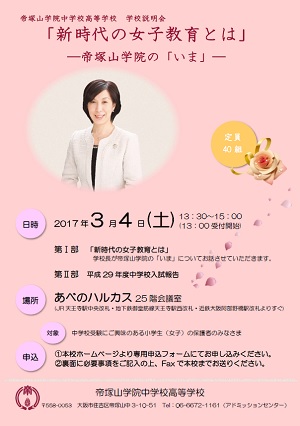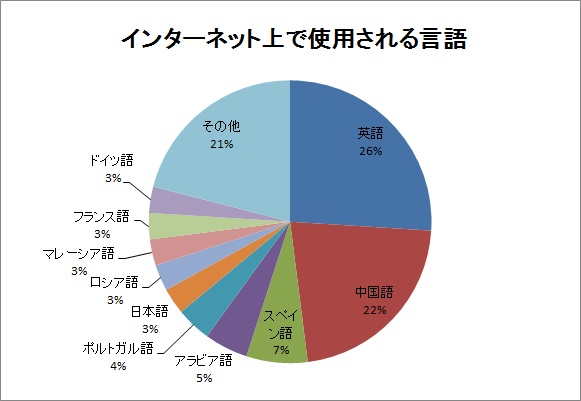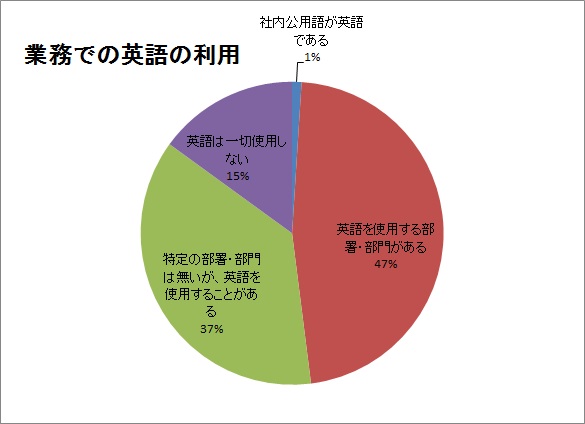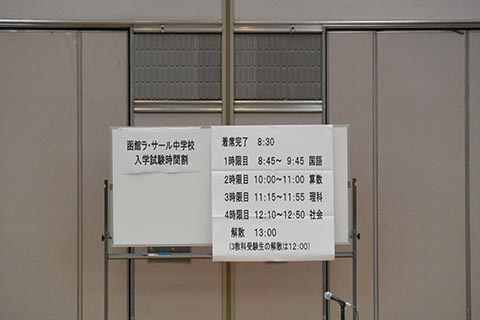1月14日・15日の行われた大学入試センター試験も終わり、私立大の出願・入試、国公立の前期試験と大学受験生にとっては慌ただしい時期になりましたが、一方で既に進学する大学が決まって残り少ない高校生活を楽しんでいる人もいます。実際にはどの程度の人数がいるのでしょうか。
1年前の資料になりますが、推薦入試で入学した学生数の資料がありましたので、紹介します。この資料は付属(附属)校や系列校からの入学者は含まず、それ以外の指定校推薦と公募制推薦を経て入学した人数をまとめたものです。(数値は朝日新聞社刊「大学ランキング2017」から引用しています。)
1位の近畿大学は受験者数でも3年連続日本一の大学ですが、実は2,687人が一般入試を経ずに入学しています。もちろんこの中には公募推薦の合格切符を手にした後で、他の大学の一般入試にチャレンジした人もいると思いますが、近畿大学が第一志望だった受験生にとっては2か月も早く進路が決まったことになります。
2位の龍谷大も、定員規模からすると多い2,000人を超える入学者が決まっていたことになります。龍谷大は仏教系の大学ですが、同じ宗派の高校を指定校として入学枠を設けているために人数が多くなっています。同じようにキリスト教系の同志社大や関西学院大も同様の指定校を持っているようです。(明日に続く)