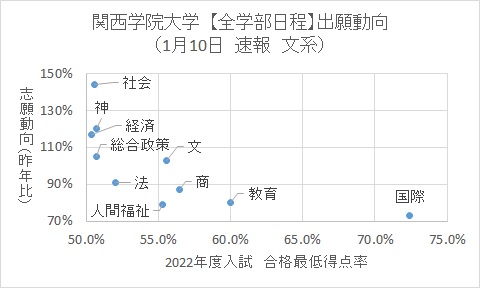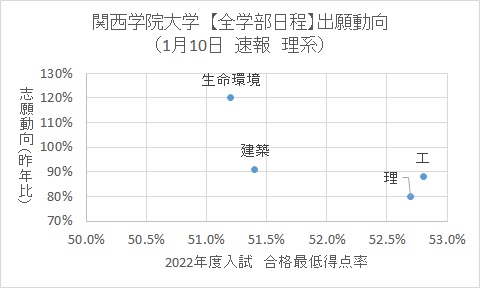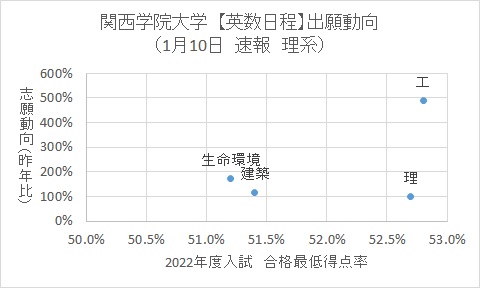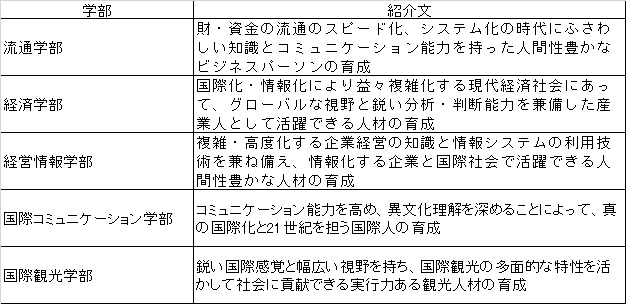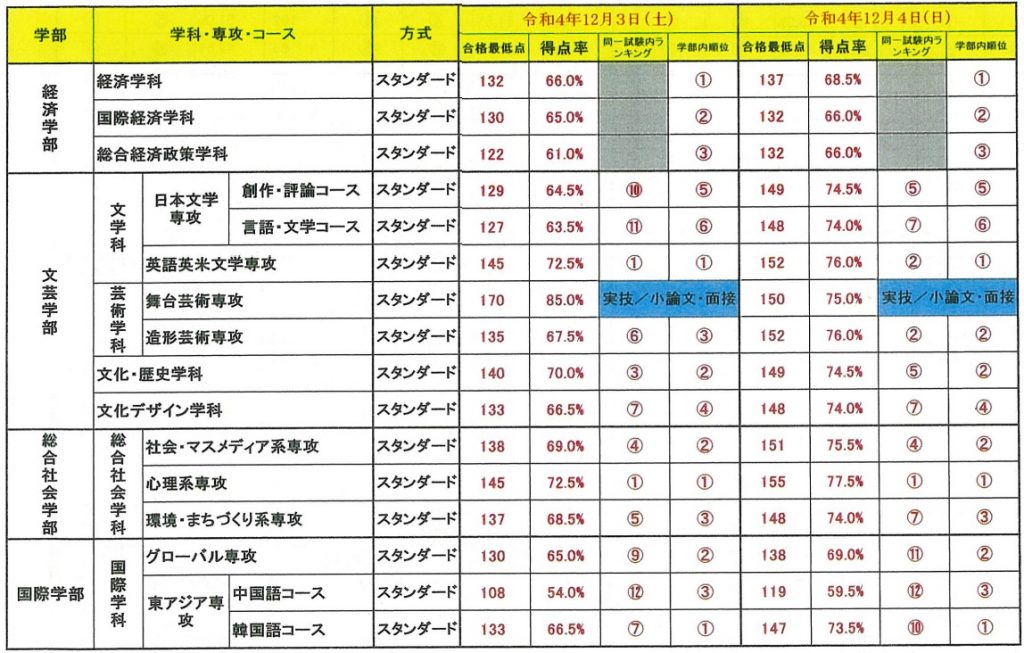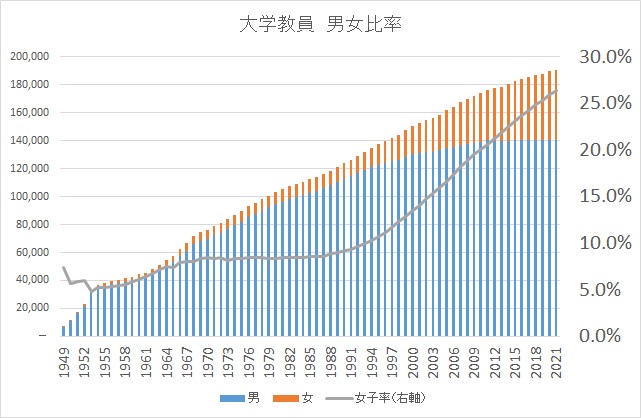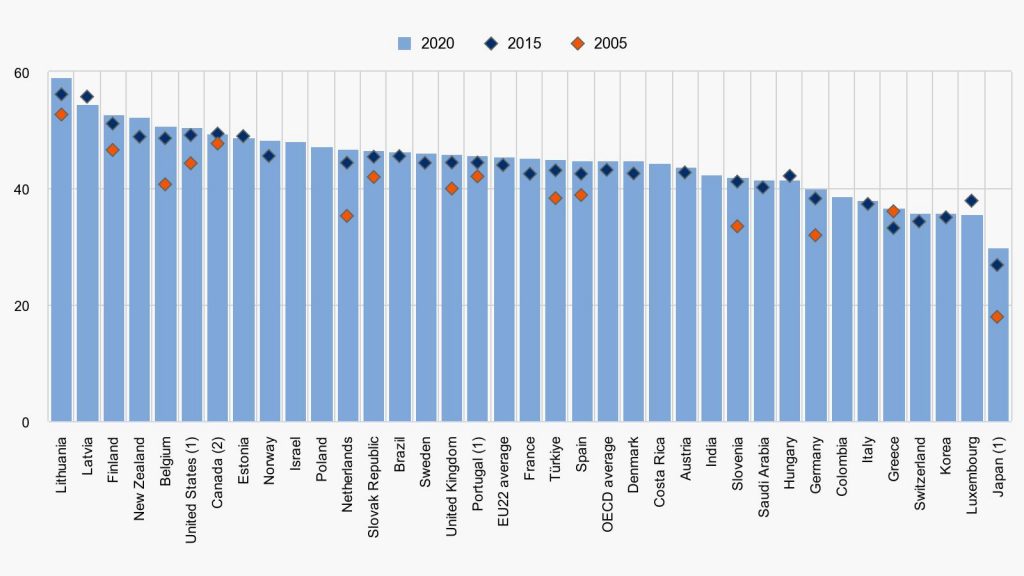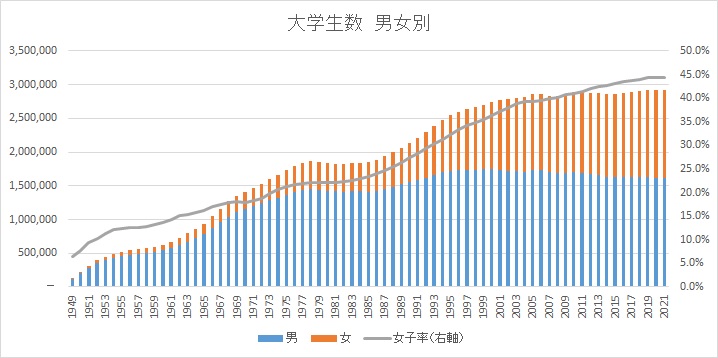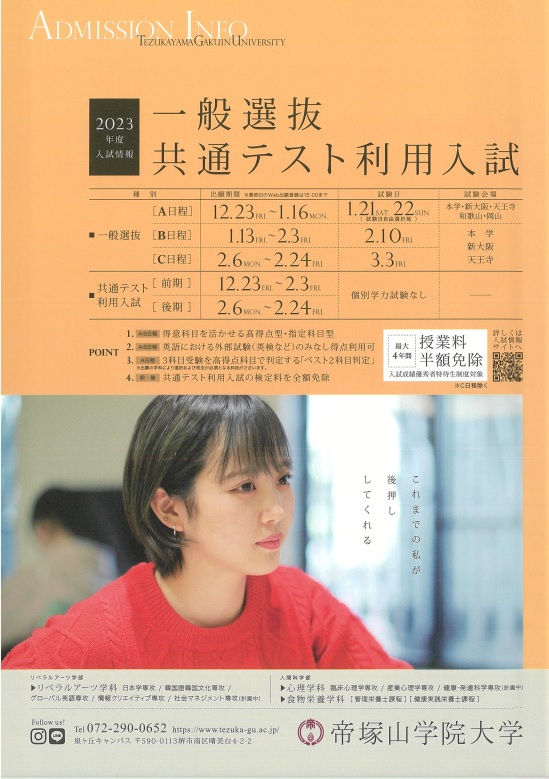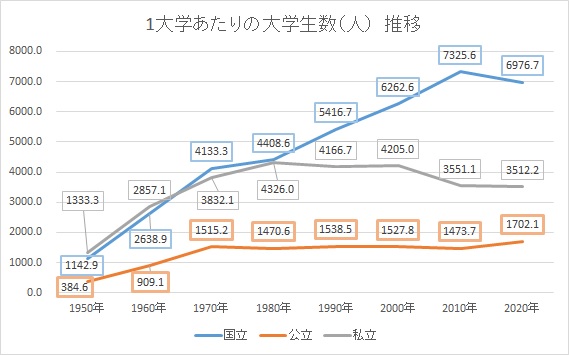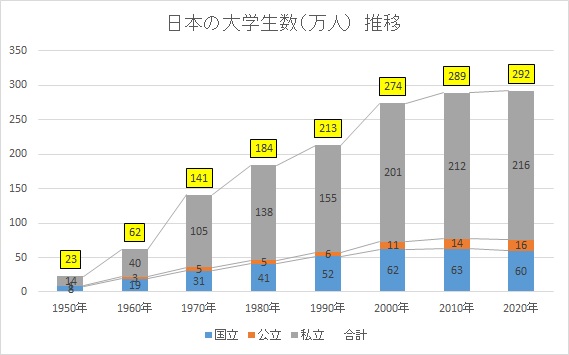新課程入試初となる2025年度入試の動向が気になるところですが、早稲田大学は2025年度入試の変更点を発表しました。
①基本的に全学部が新教育課程に対応した出題範囲で試験を実施する
⇒例えば今の高校1年生は、2年生からの歴史の選択で日本史か世界史のどちらかを選択することになっても1年生で必修科目の「歴史総合」を学んでいますので、共通テストはその範囲に関しては日本史・世界史融合問題となるわけですが、早稲田は歴史に関しては「世界史探究」「日本史探究」の範囲のみと発表しています。但し、地理に関しては「地理総合」も範囲に含まれるようです。
数学の試験範囲は文系であっても数学C(ベクトルのみ)が含まれることになります。
★但し、2025年度入試のみ、旧課程と新課程の共通範囲からの出題となります。つまり1浪(現高2の学年)までは救済されることになります。
②共通テストの「情報Ⅰ」の利用する学部、方式を設ける
⇒政治経済学部、国際教養学部、文化構想学部、文学部の4学部とスポーツ科学部の共通テスト+競技歴方式で共通テストの「情報Ⅰ」を選択科目に含める、とのことです。必須ではありませんが、選択できるということは、当然共通テストの「情報Ⅰ」に向けて準備をしてこの科目を受験することが求められているということになります。
③社会科学部と人間科学部では一般選抜を共通テスト+学部独自試験方式に変更
⇒センター試験、共通テスト利用に積極的な早稲田が、さらに共通テスト利用に重心を移したかたちです。
④商学部で一般選抜の英語4技能テスト利用型の募集を停止、一方で文化構想学部や文学部では、英語4技能テスト利用方式の募集人数を増加。
⇒学部間で英語4技能テストへの評価が分かれています。
⑤国語の出題範囲は「国語表現」以外の5科目です。
⇒新たな教育課程の国語では、「現代の国語」「言語文化」が共通必履修科目で、「論理国語」「文学国語」「国語表現」「古典探究」の4科目は選択となっています。早稲田は「国語表現」以外の5教科を試験範囲として発表しました。つまり「文学国語」も含まれますので、要注意です。
他大学の、今後の議論にも影響を与えそうな内容となっています。これから各大学からも順次発表が行われると思いますが、試験範囲や共通テスト利用についてなど、詳細情報にも注意しておきましょう。