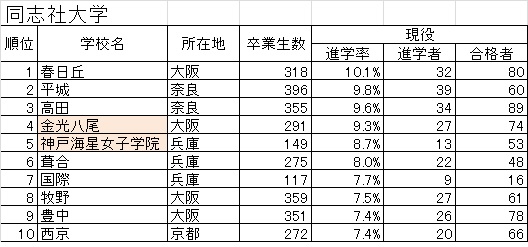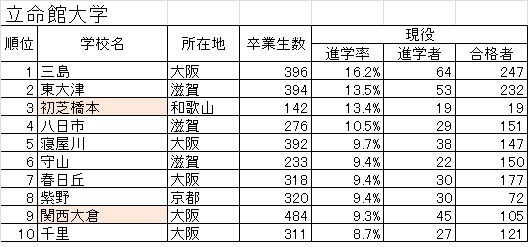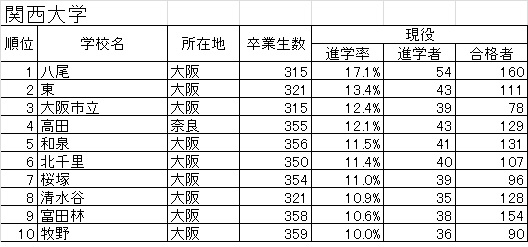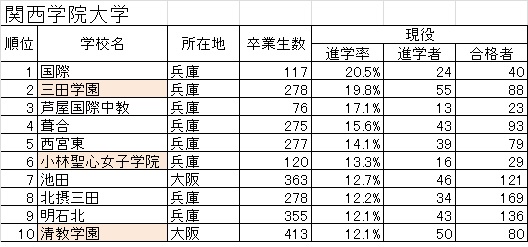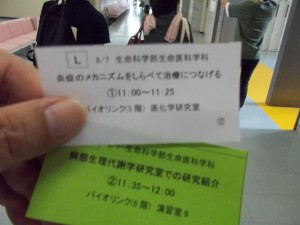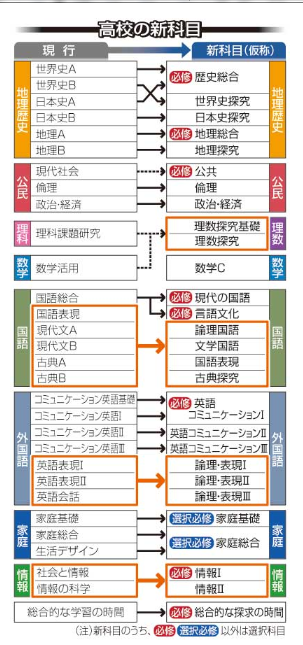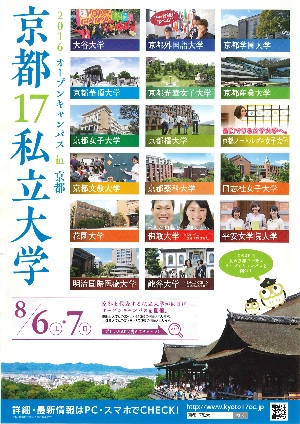大阪府松原市の阪南大学は、51年前の1965年に設立された文系の大学です。創立当初は商学部からのスタートですが、今では「経済学部」「流通学部」「経営情報学部」といった商業系の学部に加えて、「国際コミュニケーション学部」「国際観光学部」の5学部を擁する、学部学生だけで5000名を超える規模となっています。(「国際観光学部」のみ少し離れたキャンパスです。)実学を重んじる「キャリアゼミ」などの教育によって就職率も高く、実就職率では関西で4位だそうです。どのような大学なのでしょうか。
大学設備をいくつか案内していただきました。
まず、人工芝のグラウンド。この日はアメフト部が練習をしていました。最近は建物ばかりの大学が増えてきましたが、このように校地の真ん中に配置されたグランドのおかげで周りの建物からの見晴らしも良くなっています。

50周年記念館という真新しい建物の3階に学生課があります。銀行の窓口のように番号札を取って順番に待つ方式です。大学の事務室も進化したものです。その外に災害用の備蓄倉庫があります。水害も想定してあえて3Fに設けたそうです。

2階には「スチューデント コモンズ」という小集団学習やネイティブによる英会話を行うスペースがあります。いくつかのガラス張りの小部屋は壁一面がホワイトボードになっており、議論や授業にも使われるそうです。

阪南大学といえばJリーガーを40名以上輩出するほどのサッカーで有名な大学ですが、スケート(ショートトラック)においても、オリンピック選手の出身校として知られています。長野五輪で金メダルを取った西谷岳文選手、冬季五輪に3度出場している小澤美夏選手のユニフォームも展示されています。

4階は記念ホールとなっており、講演などにも使える仕様となっています。
勉強の設備と同じくらい欠かせないのが食堂です。学内には食堂、カフェテリアが3か所あります。大学生協の購買では文具や書籍はもちろん、スーツまで注文することができます。
最後は図書館。2層の開架式の図書館です。DVDの鑑賞ができるソファーのコーナーまであります。社会での「実践力」にこだわる大学らしく、ビジネスソフトのマニュアル類なども充実していました。
次の日曜日に今年度最後のオープンキャンパスが行われます。高校生の皆さんは、この就職に強いという大学を自分の目で確かめてみてはいかがでしょうか。