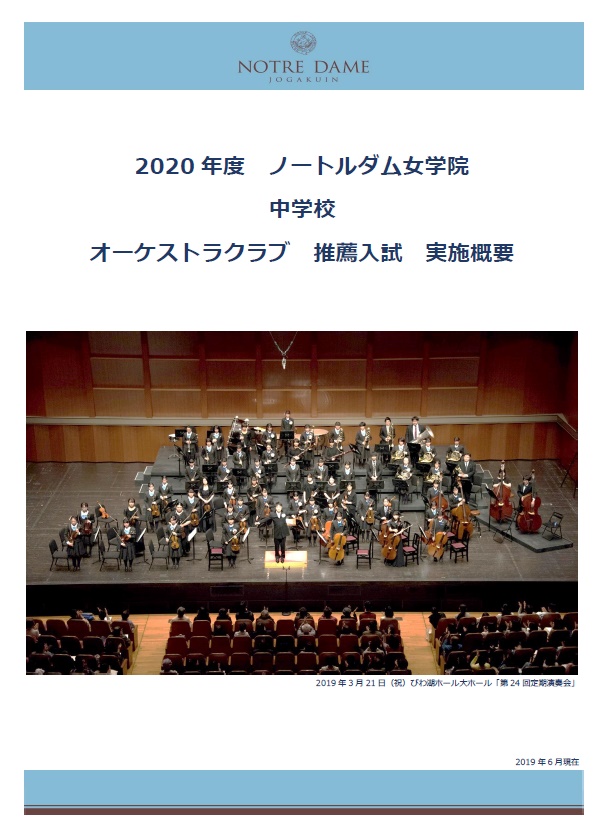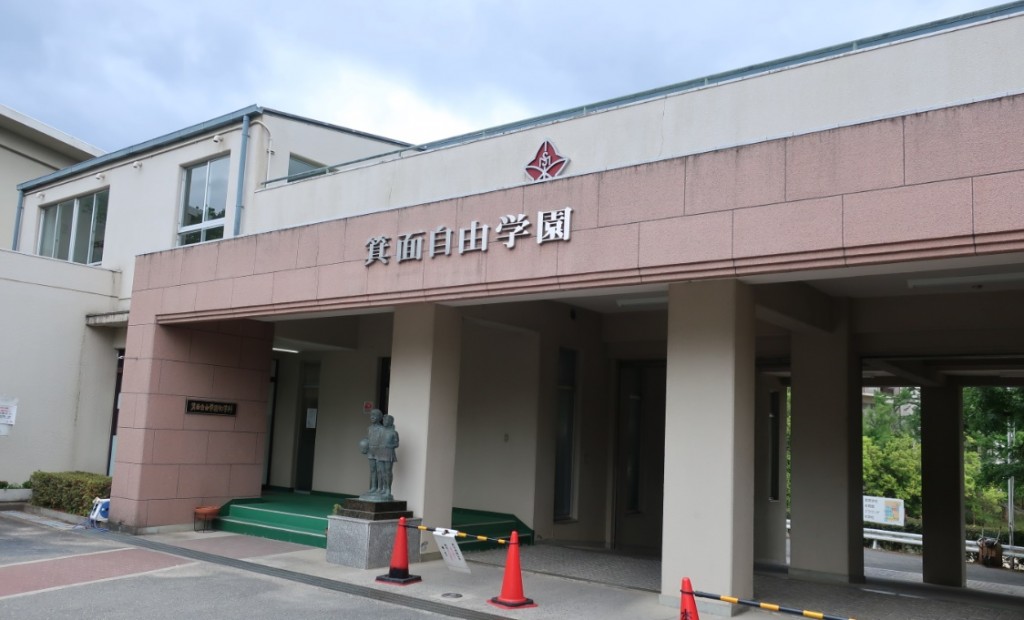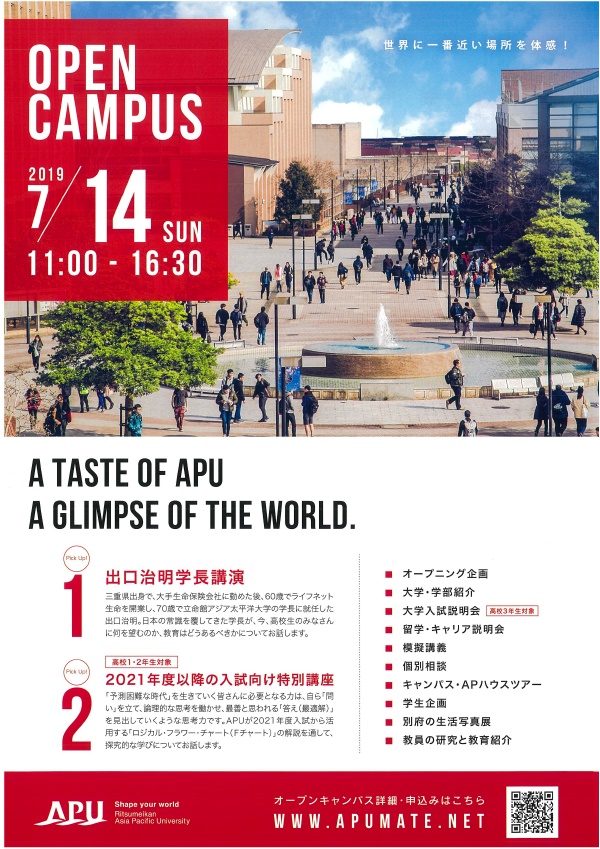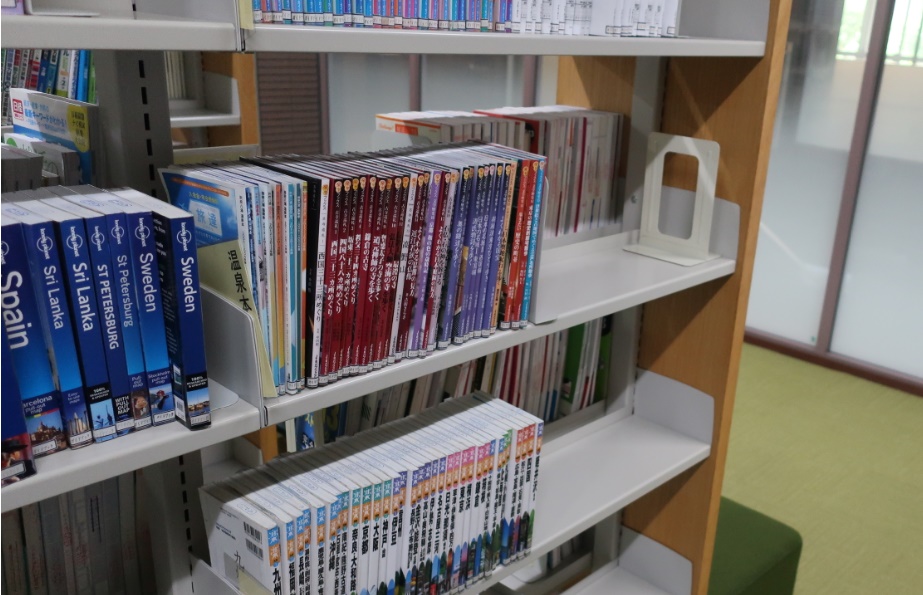京都のイメージといえばお寺や神社、和服や茶道など伝統的な和のイメージが強いのですが、実は西洋音楽が盛んな地域でもあります。日本で最古の自治体直営のオーケストラである「京都市交響楽団」を始めとして、100周年を迎えた京都大学交響楽団、毎年ヘンデルのメサイア全曲演奏を行う同志社大学、こちらも60年以上の歴史のある立命館大学、さらに龍谷大学、京都産業大学、京都女子大学、京都薬科大学、京都教育大学にもそれぞれオーケストラがあり、京都府立医科大学、京都府立大学、京都工芸繊維大学は合同で「京都三大学交響楽団」を構成しています。
中学校、高等学校でも洛星、京都女子、ノートルダム、同志社、同志社女子の5校にオーケストラ部があります。つまりそれほど広くもない盆地に、プロオケ1つ、大学オケ9つ、中高オケ5つ、その他それらの卒業生たちが作ったアマチュアオケを含めると、数十のオーケストラがひしめいているという不思議な街です。
そんな京都ならではの企画なのですが、以前このエントリーでも紹介したノートルダム女学院中学校・高等学校では、入学段階でオーケストラに入りたい女子への優遇策が発表されました。
詳細は学校ホームページから要綱を確認していただきたいのですが、オーケストラで使われる楽器(バイオリンなど)だけでなく、中学入試ではピアノやエレクトーンでも楽器経験があればOKであるようです。何らかの楽器を習得した生徒なら、別の楽器に取り組んでも成長が早いわけですから納得です。
というわけで、こちらのエントリーは10月1日と早めとなっておりますので、お気を付けください。
(画像をクリックするとPDFが開きます。こちらは中学入試用で、高校入試用のものは別に学校ホームページに掲載されています。)