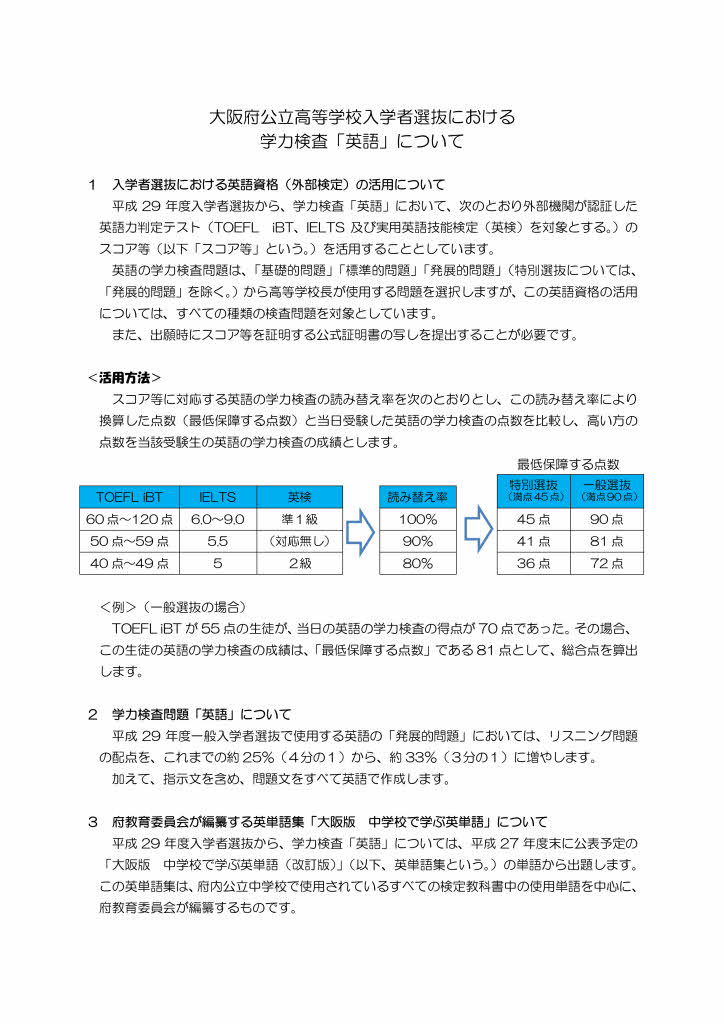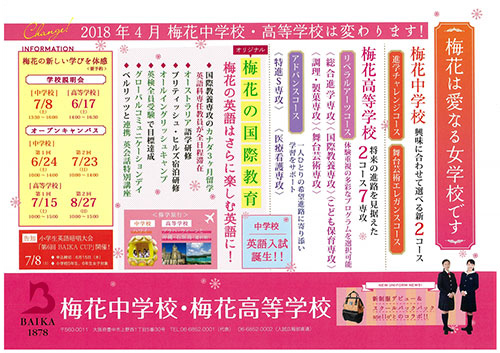大阪では国公立大学・理系進学へ強い(というよりトップの)女子校として君臨している四天王寺中学校・高等学校ですが、この学校や生徒に対して「まじめ」「勉強中心」といった印象を持っている受験生が多いように思えます。
まずは、大学合格実績から・・・
今年度は[理数コース]1期生の卒業初年度となり、在籍30名に対して、
○国公立大学+大学校合格数 17名
○医学部合格数 6名(うち医学科4名)
○薬学部合格数 5名
○関関同立合格数 16名
となりました。
卒業生470名に対し、国公立大学医学部医学科合格数は50名(現役26名)となっています。つまり、1割以上が医学部という近畿圏の女子校としてトップレベルの割合となっています。(本当は神戸女学院もこれを超える実績かもしれないのですが、神戸女学院は大学進学実績を全く公表しない学校なので比較できないのです。)
また、他の学部を含めて、国立大学合格数は、155名(うち現役92名)、公立大学合格数は、79名(同57名)となっています。
中学から入学した生徒のみならず、高校からの入学した生徒もこれらの実績に大きく寄与しています。確かに、この実績からすると、大学進学(特に医学部系)に向けた取り組みを大切にしていることは間違いありませんが、この学校はそれだけではないのです。
★[医療の現場体験]➡四天王寺病院見学 2016/7/26実施
★[海外語学研修]➡オーストラリア・ブリスベン14日間予定
★[最先端の医学ってスゴい!!]➡京都大学医学部・医療体験ツアー 2016/8/29実施
★[大学へ出かけて勉強だ!]➡京都大学法学部ツアー&近畿大学医学部ツアー2016/12/16 実施
★[校内語学研修]➡英語づくし! 2017/3 習熟度別クラスで5日間実施
★[キャリア講座]➡“公認会計士の仕事と魅力”の説明会&座談会 2017/3/8 開催
などと、体験・見学・参加型のイベントが盛りだくさんです。医学部志願者が多いこの学校ならではの体験イベントもありますが、文系の生徒向けのイベントも多く、大学進学を早くから意識させ、勉強へのモチベーションを上げる仕掛けとして機能しているのでしょう。
一方、部活も元気です。
★コーラス部(昨年夏には「声楽アンサンブルコンテスト全国大会」へ大阪代表として出場しています。今年の夏の甲子園、開会式と閉会式でも歌うそうです)
★囲碁部全国大会出場(女子では珍しいそうです。)
★自然科学部生物班が日本生物学オリンピックで入賞!
★今年のインターハイ(南東北総体)にはバレーボール、ハンドボール、体操、卓球、バトミントンが出場!(スポーツ・芸術コースの生徒もがんばっています。)
★放送部は「NHK杯全国放送コンテスト」に出場!
その他文化系では、筝曲やダンス、茶道などの部活も盛んですが、それに加えて弦楽器同好会も人数を増やしており、部活動には消極的な進学校が多い中で、むしろ次第に充実してきているように見えます。
と、いうわけで、是非一度、説明会などの機会に学校を訪れてみましょう。