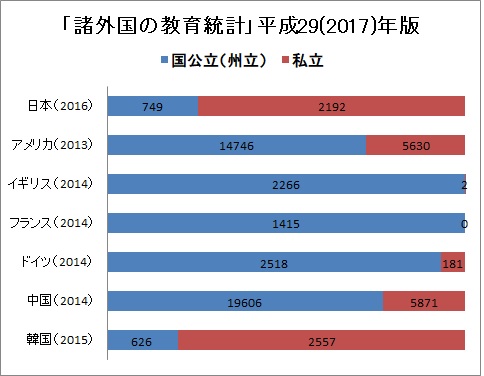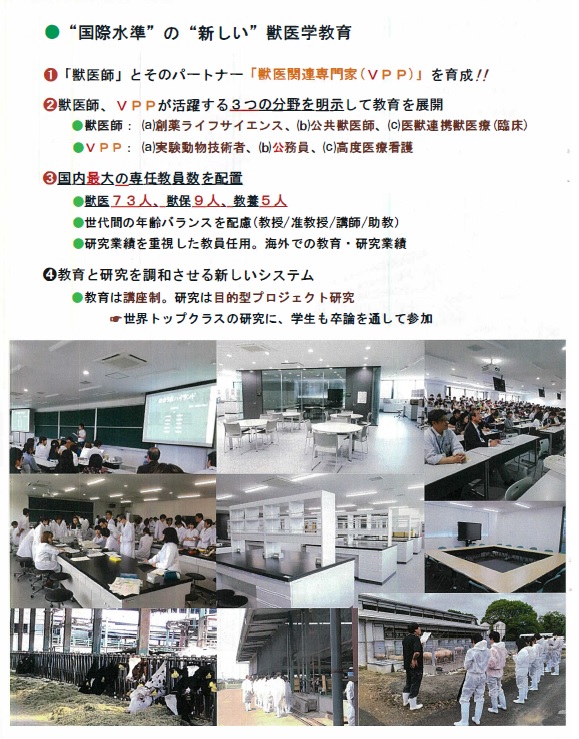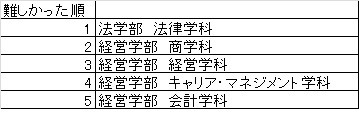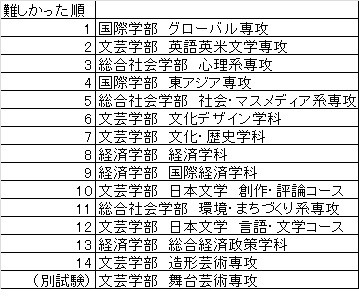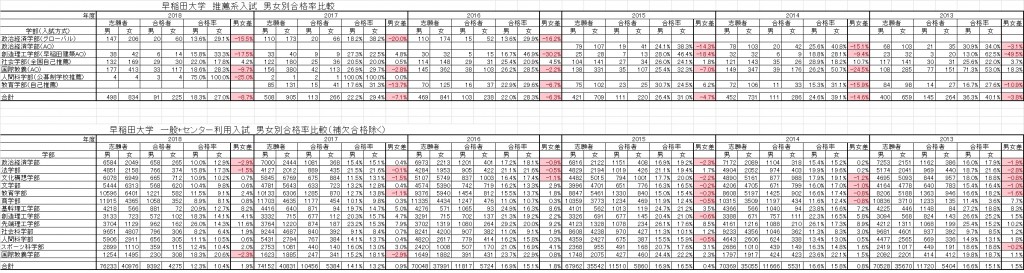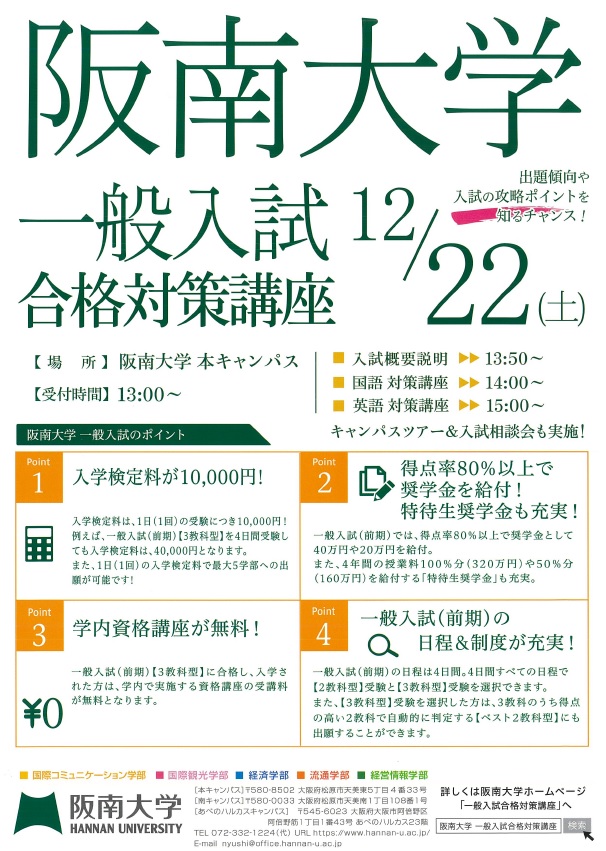今回は滋賀です。
こちらでは立命館大が1位で同志社大が2位。立命館大と違って同志社大は滋賀にキャンパスがありませんから当然でしょう。しかし、その差は2割もありませんのでやはり同志社の層の厚さを感じます。3位は滋賀医科大。これも京都の京都府立医科大と同じような理由ですが、これまた1学年の募集が100名と、京都府立医科大と同じような規模です。そう考えると逆に少ないなぁ、という話になりますが、滋賀医科大は「国立」で、もう40年も前の事ですからこの格付けを覚えている人も少なくなりましたが、実は「旧一期校」です。というわけで、卒業後、京都大の医局に属する医師も多く、その分滋賀に留まる率が下がるというわけです。
最後に奈良です。
2位の2倍以上と圧勝の近畿大が1位。近畿大の農学部や附属小学校は奈良にありますし、東大阪の本部も近鉄沿線にある近畿大学にとって奈良は「ほぼ地元」だと考えると納得できます。2位は奈良県立医科大、僅差で同志社大、関西大と並びます。京田辺キャンパスを持つ同志社も、近畿大と同じように「ほぼ地元」といえますが、距離的に離れている関西大がほぼ同じ人数だというのは評価されるべきところでしょう。
5位にはこういうランキングには珍しい理工系大学である大阪工業大学がランクインしています。大阪のランキングをお見せした時には突っ込みませんでしたが、大阪でも6位入賞です。実は大阪工業大学は実就職ランキングで連続8年間関西1位にランクインしており(大学通信調べ)、全国社長数も2000名弱と、全国の理工系大学では東京理科大学に次いで2位という大学なのです。こちらも元気のある大学として注目株ですね。
このようなランキングも、見ようによっては大学の歴史や背景などを再認識することができます。
2018年のブログもこれで最後です。ご愛読いただいた皆様には感謝いたします。次回は1月4日にお会いしましょう。良い年をお迎えください。
![]()