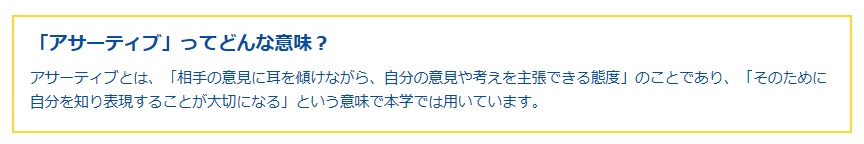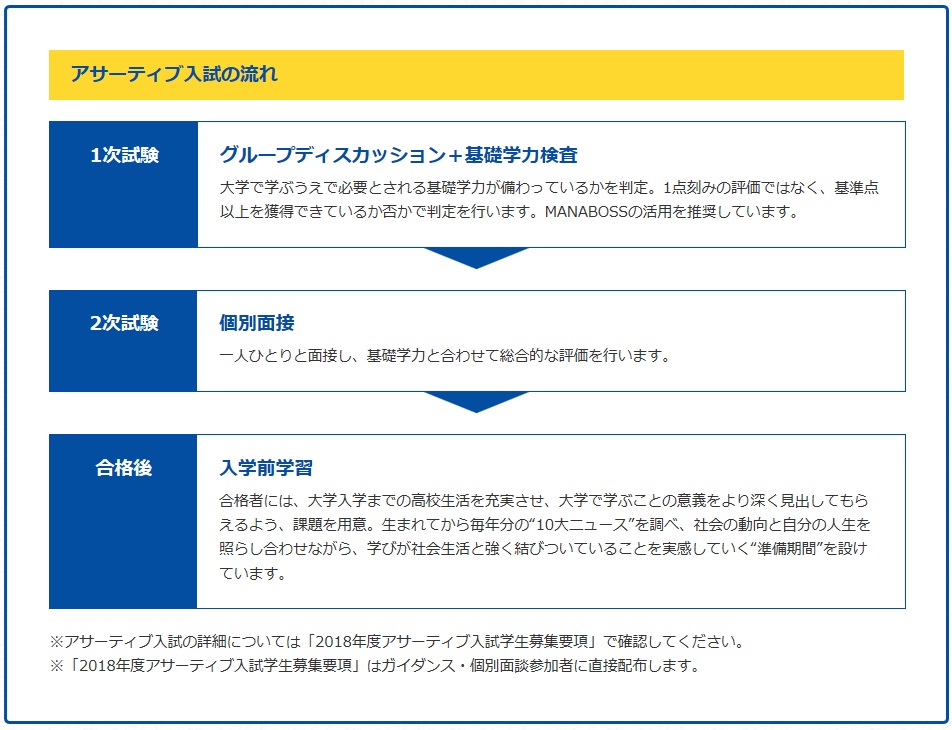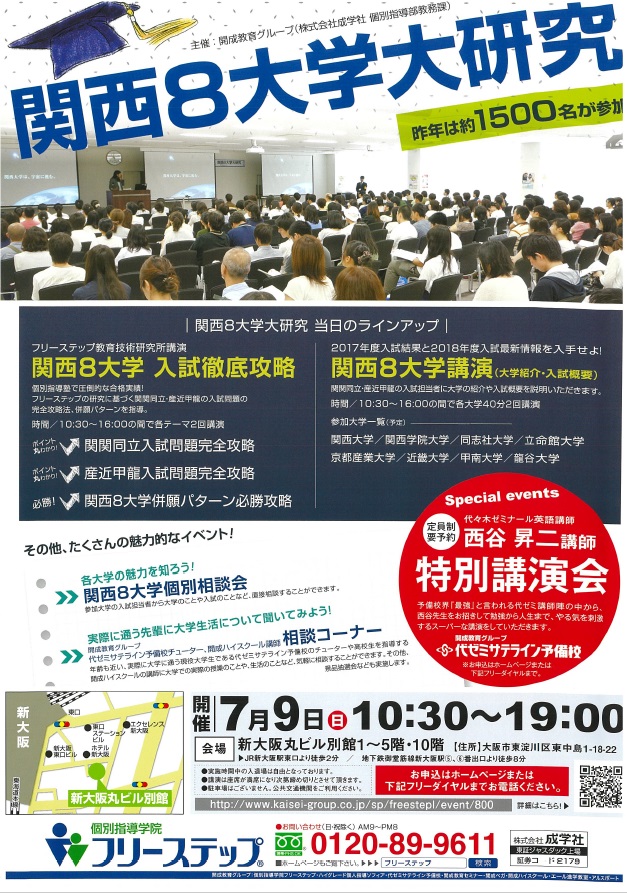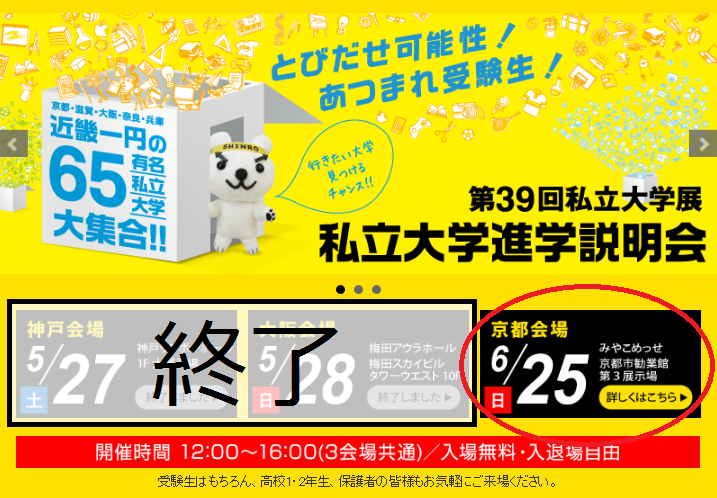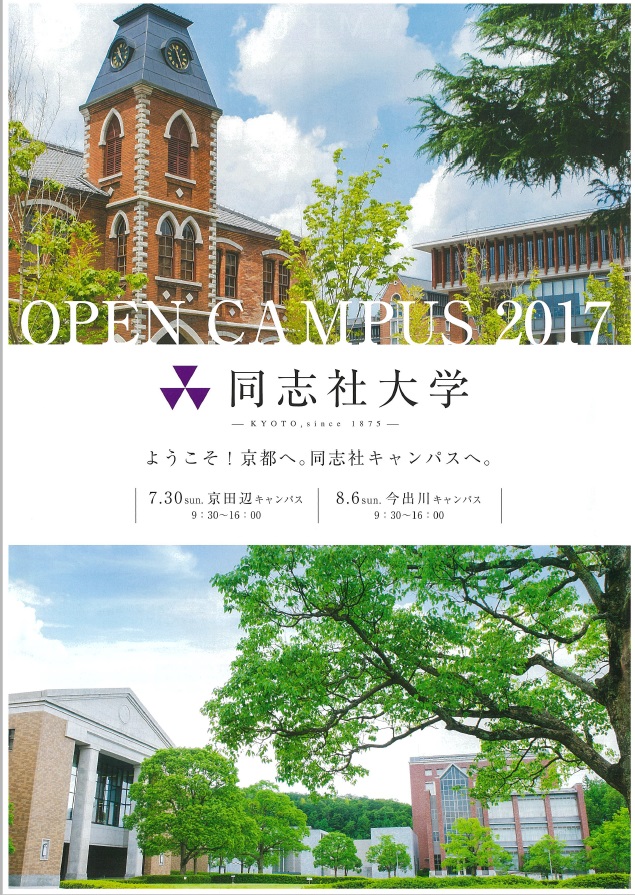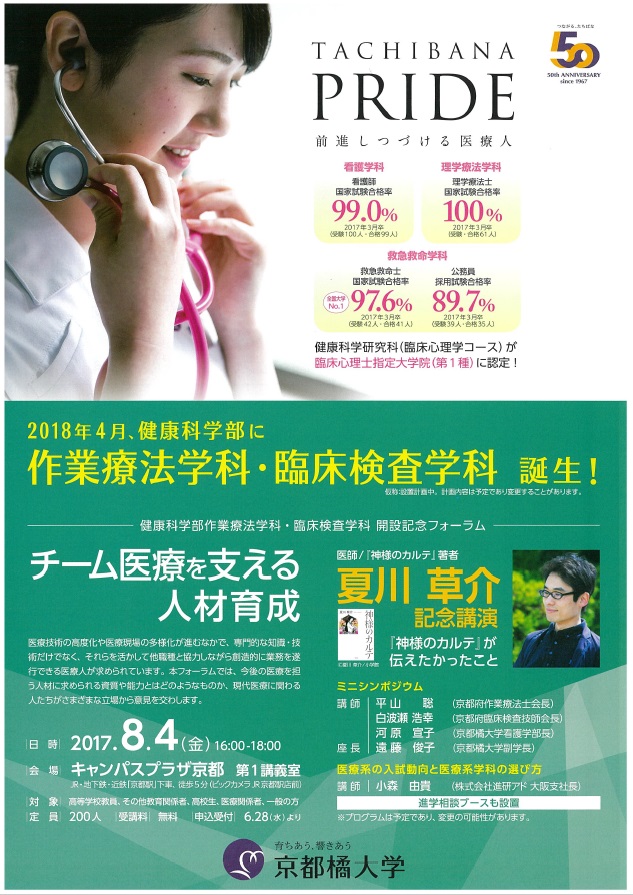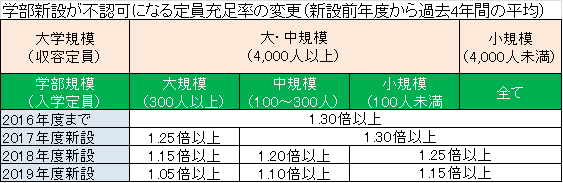以前、このエントリーでも大阪大学の世界適塾入試の出願ハードルが下がることをお知らせしましたが、第1次審査の書類選考で選ばれても、第2次選考で行われる面接・口頭試問をクリアしなければ合格はできません。そこで、このブログをお読みの志願者の皆さんへ、こっそりその第2次選考の様子を詳しくお伝えしましょう。
今年度、基礎工学部へ合格した受験生からのレポートです。
- 電子機器(携帯電話など)はすべて封筒に入れるよう指示されます。待合室に誘導されます。
- 30分ごとに10人ずつ(電子物理・化学・情報は各2名。システム4名)が資料観覧室に移動し、20分間資料を見る機会が与えられます。
- そこに用意されているメモ用紙に「口頭試問で答える問題」と「一番興味を持った問題」を選んで記入します。「垂直跳びの重心の位置と床からの効力の関係」「濃度不明の塩酸の滴定法」などの問題が用意されています。
- 一人ずつ面談会場に誘導されます。
- 試験官は4名と案内のスタッフ1名の5名が部屋の中にいます。受験生の前に机、横に荷物置きが用意されています。
- 最初の10分間は志望動機や将来の職業、アドミッションポリシーのどれに一番当てはまるかなどの面接が行われます。調べ物の手順などについても聞かれます。
- 次の10分で口頭試問となります。選んだ問題について答えとその根拠を口頭で説明します。
- 面接終了後、面接終了待合室に移動します。
- 全員揃ったところで、建物の外まで誘導され、そこで解散となります。(先に終わった人が情報を漏らすことができないような配慮だと思われます。)
と、いうわけで、少しは当日の様子が伝わったでしょうか。他の大学ですが理系の推薦入試では観察力を測るためでしょうか、住所地の近くの河川の水深や、受験会場前の廊下に貼ってあるポスターについて質問される例もあるようです。常に周りのものを観察し、疑問を持つという習慣も有効かもしれません。理系の推薦入試を考えている皆さんは、今日から視点を変えてみましょう。