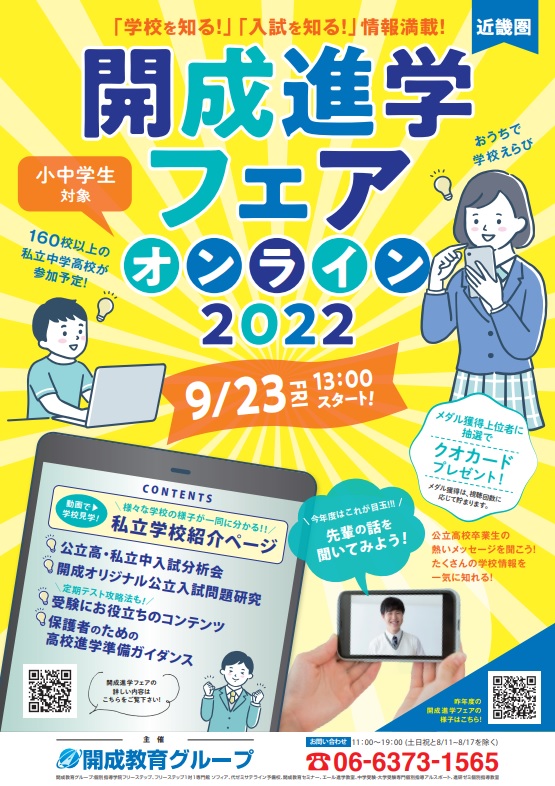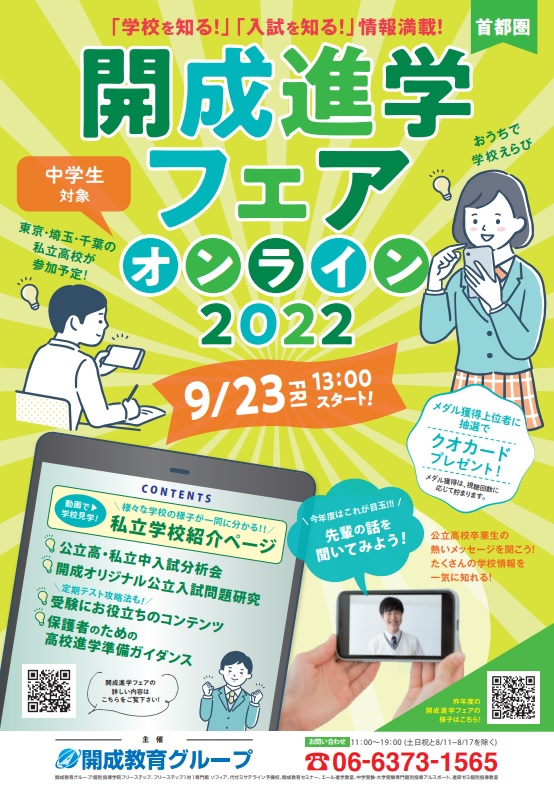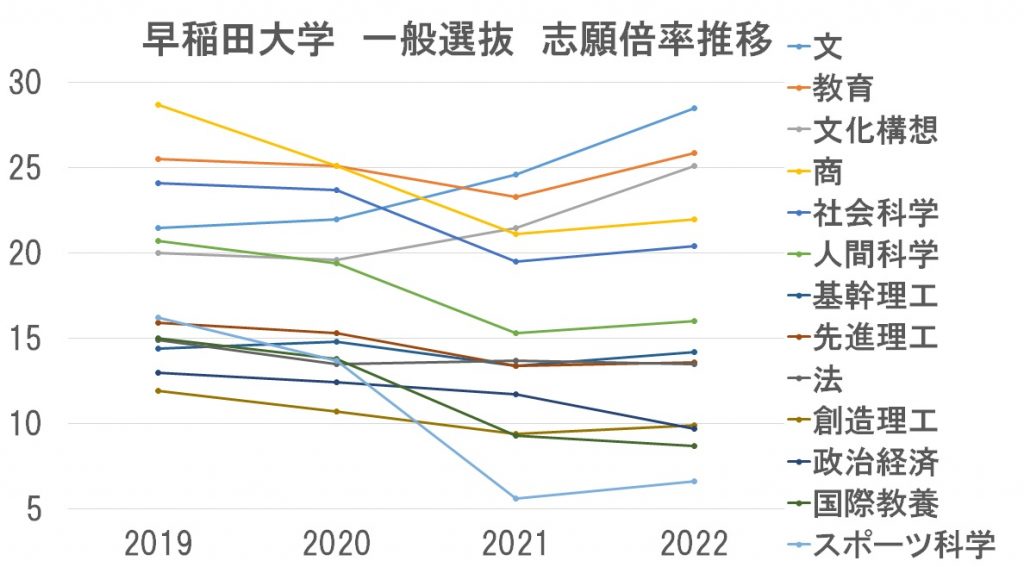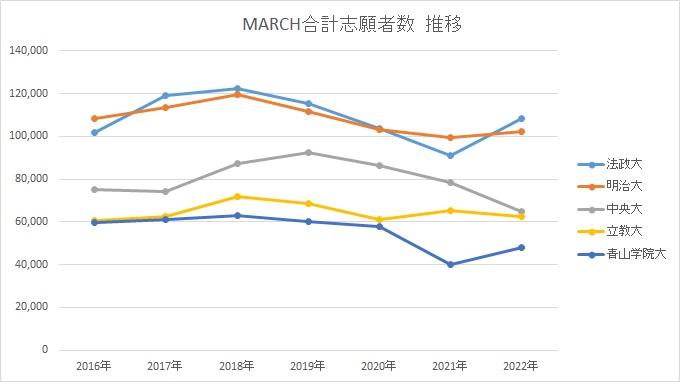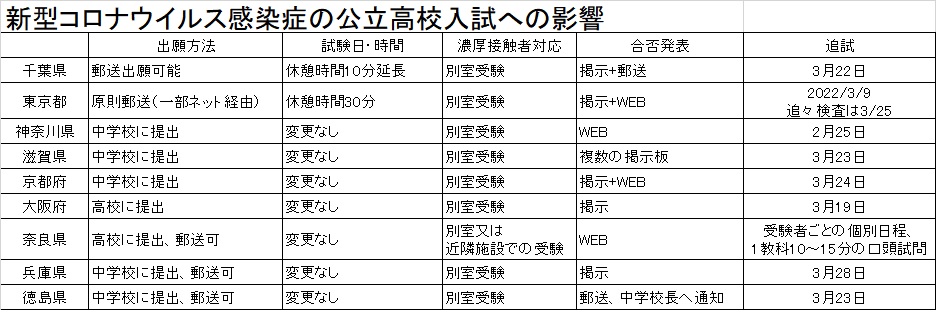東京都北区のJR王子駅前に王子神社がありますが、その隣という環境&利便性抜群な場所に順天中学校・高等学校はあります。実はこの学校、1834年(天保5年)に大阪市南本町(相愛中高の南側)に創設された私塾をルーツとしますが、1871年(明治4年)に東京に移転して旧制中学校へと発展し1953年(昭和28年)に現在の校地に移転したあと、なぜか一度女子校となります。その後1990年(平成2年)に共学化され、さらに中学校を併設してSGHにも指定されるなど発展を遂げてきました。卒業生数は毎年250名前後といった規模ですが、毎年国公立に30件前後、早慶上理ICUに70件以上といった合格実績の進学校です。ルーツとなった私塾のスタートから計算すると189年の歴史がある超伝統校ともいえます。
因みに医学部をはじめとする医療系の学部が多い「順天堂大学」とは関係ありません。
さて、この順天中学校・高等学校を運営する「学校法人順天学園」が北里大学を運営する「学校法人北里研究所」と法人合併に向けた協議を開始するとのお知らせが入りました。
986b81bc7a4b9062d02dd6d71cee9a5d-1.pdf (junten.ed.jp)
このニュースリリースによると存続法人は「学校法人北里研究所」になるとのことですので、実質的には順天中高が北里大学の傘下に入るという形になりそうです。
北里大学も医学部をはじめとする医療系の学部に加えて、獣医学部や海洋生命科学部など全国的にも珍しい学部も設置している大学で、進学校としての順天中高との親和性も高いのでしょうか。将来的には順天高から北里大学への推薦枠が設定されるかもしれません。そうなれば順天中高の人気がさらにUPするかも、というお話でした。