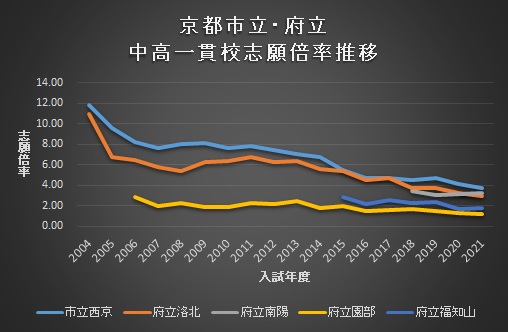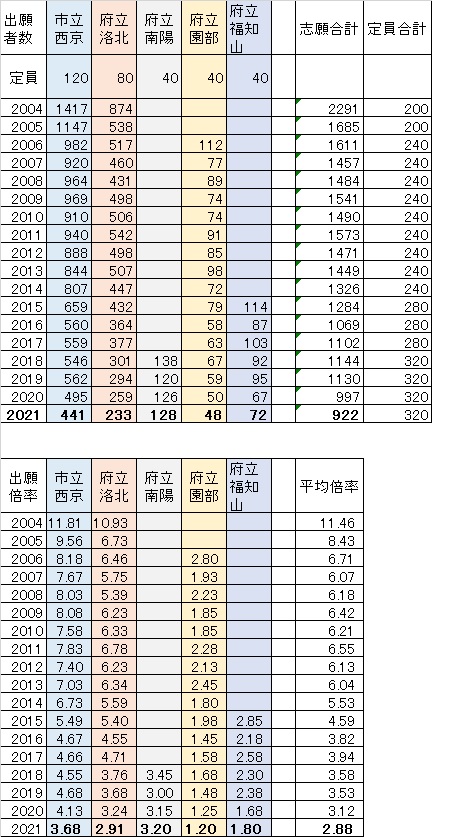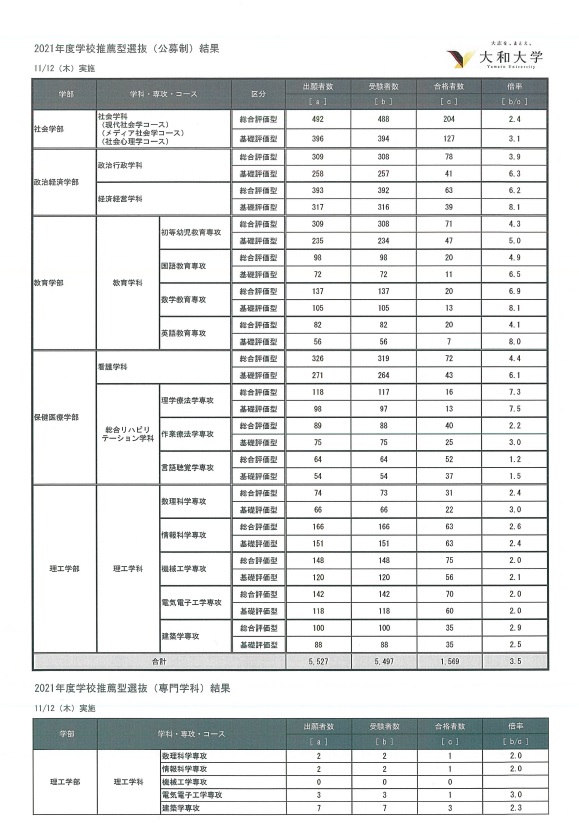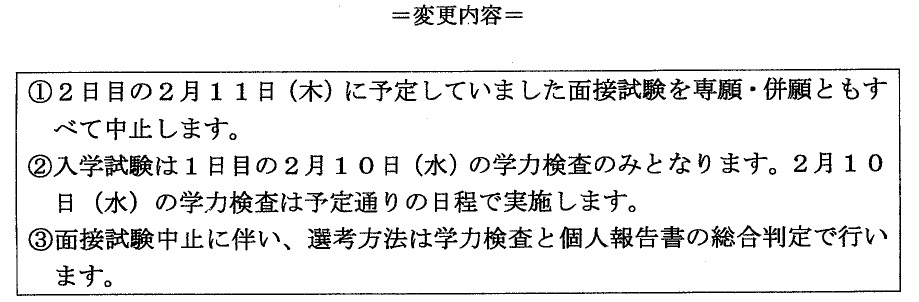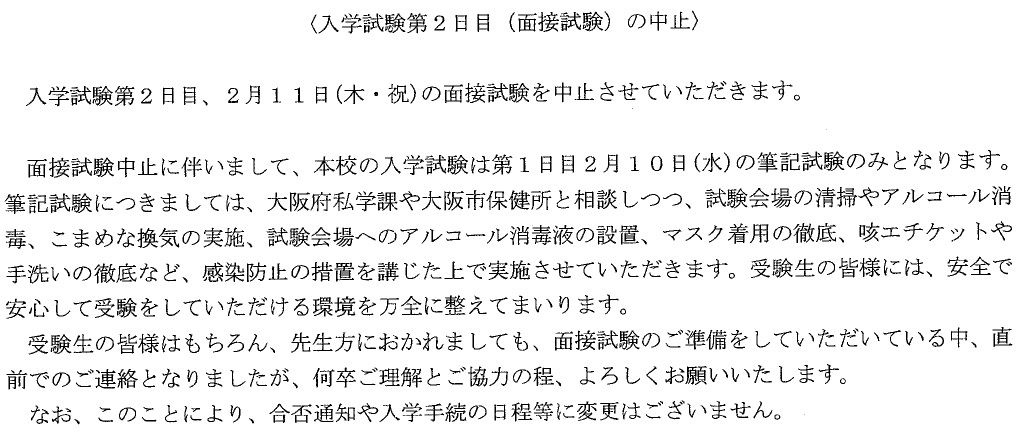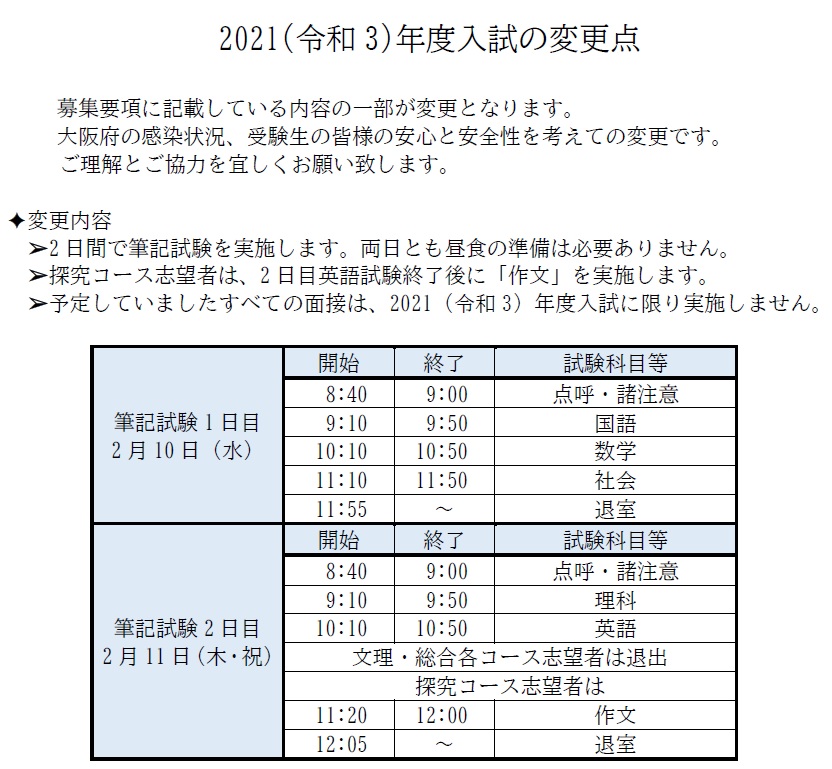思えば1年前、2020年がこんな年になるとは思いもしませんでした。東京オリンピック・パラリンピックも開催され、海外からの入国者数も史上最高!教育の世界でもグローバル系学部の人気がうなぎのぼり・・・のはずが、世界の環境が一変してしまいました。
実は102年前の1918年3月、アメリカが起源の新型ウイルスが第一次世界大戦の出兵によってヨーロッパに持ち込まれ、世界各地でのパンデミックへとつながっていきました。感染情報が当時中立国だったスペインから発表されましたので「スペイン風邪」と呼ばれますが、そこから2年の間に世界で1億人が亡くなったともいわれています。当時の人たちもワクチンや治療法がない中で、ウイルスに関する知識もないまま、ひとまずマスクは必須、という生活が強いられたようです。
日本では当時の人口約5500万人の約43%が感染し、39万人が亡くなったとされていますが、その結果集団的な免疫を獲得し、流行はそこで一気に下火になります。その直後の1925年に大阪と東京でラジオ放送が開始されました。最新の情報や娯楽を「密」にならずに楽しめるという新たなメディアは大歓迎され、人々の生活が一変し、その後テレビにつながるマスコミュニケーションへと発展してきます。(但し世界で悪化した経済状況が第二次世界大戦につながり、各国で国民を煽動するためにもラジオ放送が使われたという負の歴史も忘れてはいけません)
さて、コロナ後の世界を考えてみますと、既にインターネットを利用した双方向通信での授業提供や会議などが一般的になってきましたが、さらにバーチャル空間でのアバターを介しての会話やホログラムなど、新たなインターフェースがコミュニケーションの形を変えていくことになるでしょう。データベースの検索やデータ解析を先回りして行ってくれるAI秘書を各自備える日が来るかもしれません。そうなれば、そこで人として必要とされる能力は知識や技能ではなく、創造性の高い分野になるわけです。(例えば、文字をきれいに正確に書く、という技術はもはやパソコンに任せておけばよいのですが、同じ文字を書くのでも一種デザイン性が求められる「書道」は無くならなかったのと同じです)したがって、教育の目指す方向も今までと大きく変わるわけです。長時間拘束と反復練習、大量の課題で知識を詰め込もうとする教育は、もはや求められていないことになります。
「学校選びの道しるべ」ブログでは、これからの100年を作っていく子どもたちのために、学校や教育に関する客観的データを収集することに加え、実際に学校に足を運んでしか得られない情報も取材し、学校選びに失敗する子どもを一人でも減らしたいという思いで、掲載を続けていきたいと考えています。今後ともお付き合いよろしくお願い申し上げます。 どなた様も良い年をお迎えください。(受験生の皆さん、今年の初詣は感染予防の観点からも受験後に行くようにしましょう)
(次回の更新は令和3年1月4日(月)の予定です)