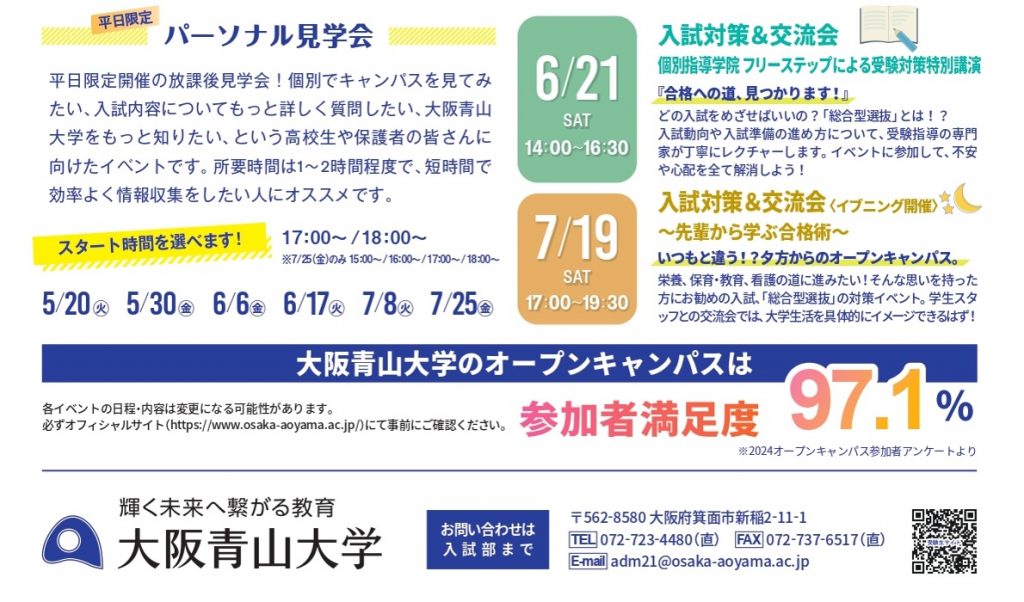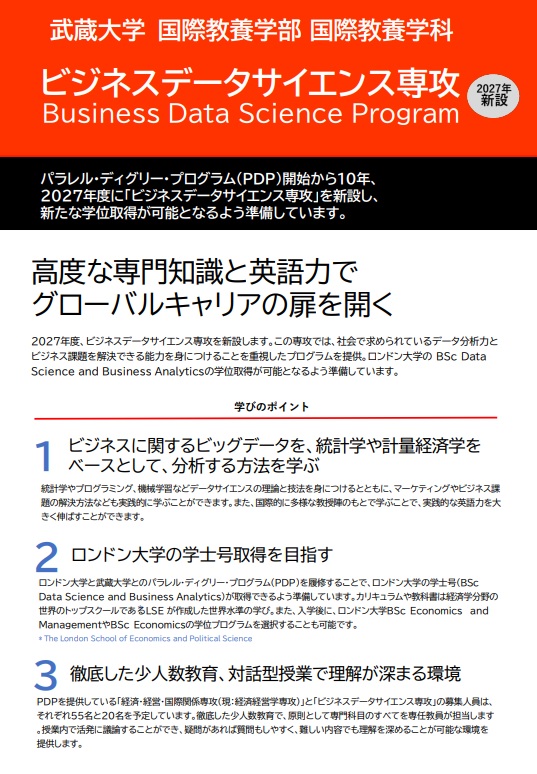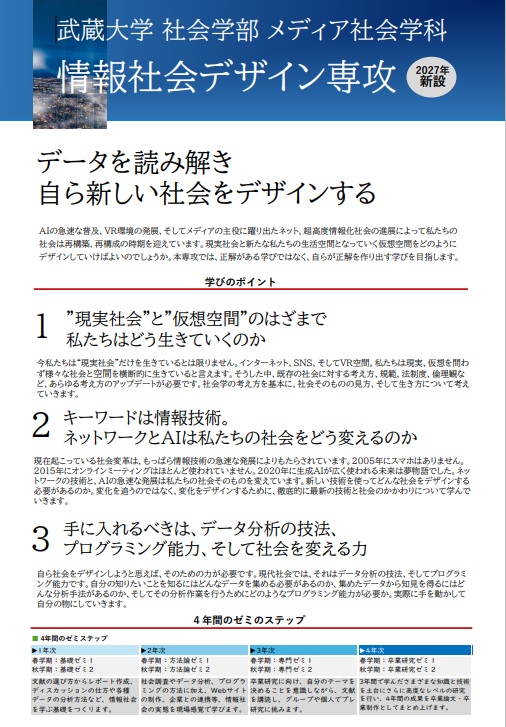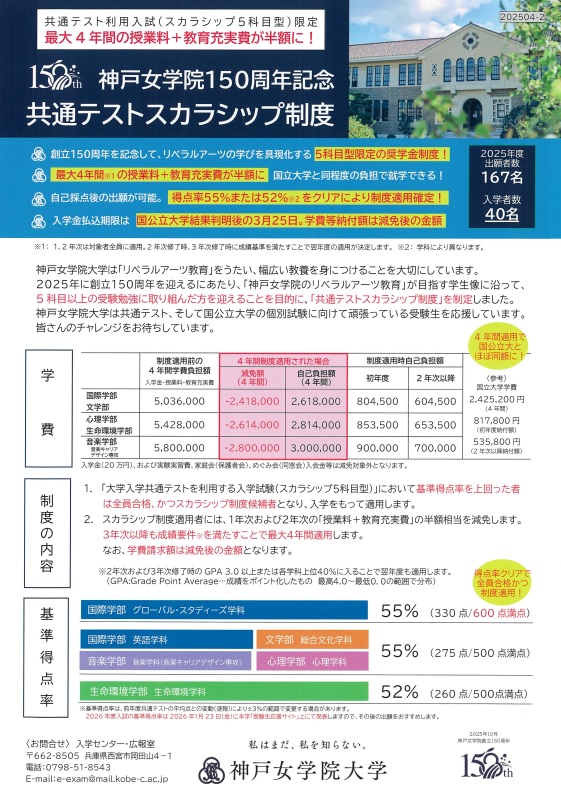立命館大学は2026年度4月、新たな学部「デザイン・アート学部」の設置に向けて、現在申請段階です。まだ認可されていませんので募集要項の発表はできません。よって、あくまでも「予定情報」としてですが、一般選抜の概要が発表されました。
180名募集のうち、一般選抜で60名募集予定。その60名の内訳は、全学統一(文系)方式で35名、学部個別配点(情報型理系)方式で15名、共通テスト3教科型で5名、後期分割方式で5名となっており、全学統一が最も大きい募集となっています。
全学統一(文系)方式の入試科目はその他の文系学部と同じですから英語120点、国語(古文あり)100点、地歴公民数(ⅠAⅡBC)いずれか1科目選択100点という配点です。
総合型選抜では65名募集予定で、その内30名が視覚表現型という選抜方法で、視覚表現(スケッチやイラスト、写真、図、表などの視覚に訴える表現に関する質疑)という選考が行われるようです。残り35名はポートフォリオ型で、事前に制作し提出したデザインやアート作品がそのコンセプトやプロセスと併せて評価対象になるとのことです。
180名から、一般選抜の60名と総合型選抜の65名を除くと、残りは55名になりますが、あとはスポーツ推薦や留学生枠、内部推薦や指定校枠などになるようです。
というわけで、視覚表現型による選抜で何かデザインを課される可能性はありますが、基本的には学力検査による入試だということのようです。
詳細は設置認可後に発表される予定です。楽しみですね。